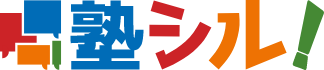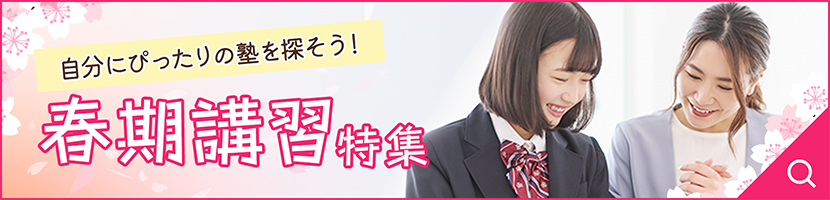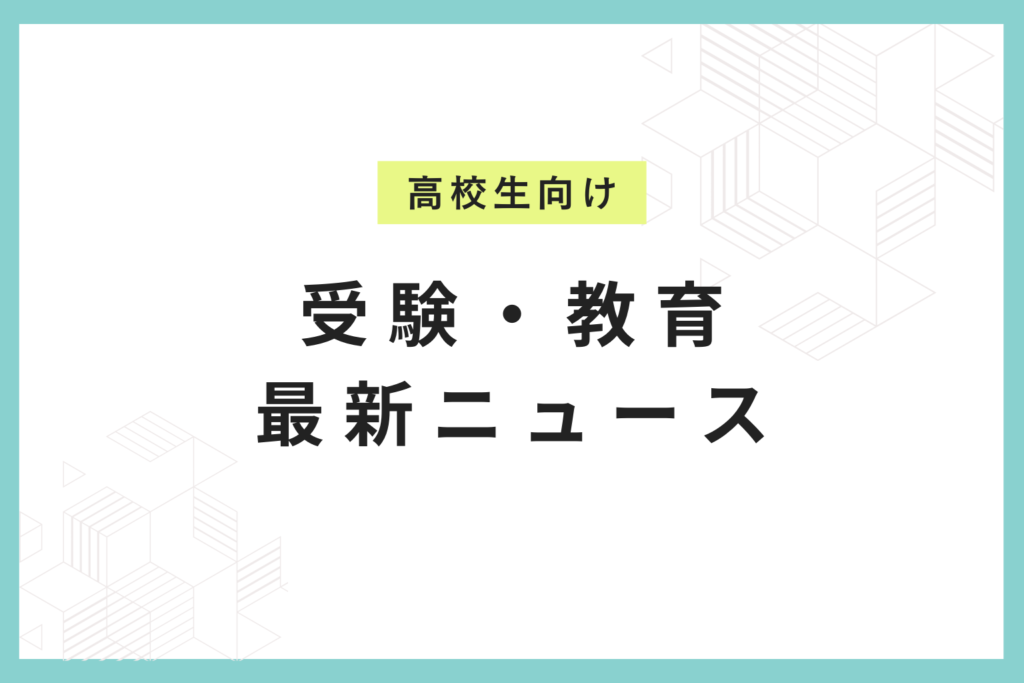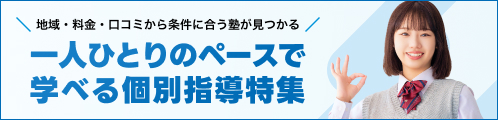高校受験の対策は中学3年生の夏からでも間に合うと言われますが、本当でしょうか?
何年生から高校受験の対策を始めれば十分に対策ができるのか、部活動との兼ね合いをどうすべきか気になる方が多いのではないでしょうか。
本記事では、理想的な学習開始時期と効果的な受験対策について解説します。
高校受験の”理想的な”勉強開始時期と学習の進め方

高校受験の対策は、できる限り早く始めるのが理想です。ここでは、公立高校を目指す場合の勉強開始時期や学習の進め方について解説します。
内申点対策は中学1年生から
内申点は、中間テストや期末テストの点数と、提出物や授業態度などを総合的に評価したものです。公立高校の受験では、内申点が合否を左右する重要な要素になります。1年生の1学期から3年生の2学期までの成績が対象となるので、1年生のうちから対策を始めましょう。
内申点を意識した生活
高い内申点を取るには、定期テストで上位の成績を目指すだけでなく、提出物や授業態度なども求められるので注意が必要です。日々の学校生活をおろそかにしないように過ごしましょう。
基礎学力の定着
中学の学習では、基礎学力を定着させることが鍵となります。特に数学や英語は積み上げ型の科目であり、1年生での遅れが後々の学習に大きく影響します。そのため1年生のうちに確実に基礎固めをする必要があります。
学力試験の対策は中学2年生の冬からがベスト
公立高校の入試では、内申点と学力試験(入学試験)の二つの対策が必要となります。学力試験の対策は、2年生の冬にスタートするのが理想です。
自分の学力を知る
学力試験対策のために、まずは自分の学力を把握しておきましょう。
学校の成績や模試の結果をもとに、自分が現在どのレベルにいるのか、志望校の合格圏内に入っているのかを確認しましょう。塾に通っている方は、塾に相談するのがおすすめです。
志望校を決める
学力を把握できたら、次に志望校を決めます。
志望校を選ぶ際には、偏差値や通いやすさだけでなく、卒業後の進路や将来の目標なども考慮に入れて検討します。情報収集には塾の開催している進路相談会などを活用するのがおすすめです。
塾には多くの進路に関するデータがあるため、たとえば「航空系の大学進学に強い高校」といった条件で高校を探すこともできます。そのため専門性の高い学科に進学したいというような場合は、塾に相談しましょう。
そのほか、難関大学を目指す場合は、その高校の進学状況なども確認しておきましょう。指定校推薦を視野に入れている場合は、高校ごとに推薦可能な大学の情報を塾に確認してみましょう。
学習計画を立てる
志望校が決まったら、学習計画を具体的に立てます。まずは、苦手教科を克服することから始めましょう。
特に、積み上げ科目である英語や数学を苦手なままにしておくと3年生になってから苦労することになるので、早いうちに解決しておく必要があります。
学習計画は、時々見直して調整することも大切です。
志望校レベル別の一般的な勉強開始時期
受験勉強を始めるタイミングは、志望校のレベルによって異なります。ここでは、レベル別の一般的な開始時期を紹介します。
難関校・地元トップ校を目指す場合
難関校や地元のトップ校を目指す場合は、できれば1年生から開始し、基礎学力を積み上げたうえで、2年生の冬から本格的な受験対策を始めるのが理想です。
1〜2年生の間は、定期試験で高得点を取り、成績上位を維持するよう努めましょう。あわせて、1年生のうちから定期的に模試を受けて、志望校のレベルと自分の現在の実力を比較しながら学習していくことをおすすめします。
中堅校を目指す場合
中堅校を目指す場合も、できるだけ早く入試対策を始めるのが理想ですが、実際には2年生の冬から始めるのが一般的です。それまでの間は、学校の授業内容を理解し、苦手分野をなくして基礎固めをしておくようにしましょう。
中学3年生の夏からでも受験対策は間に合う?
部活動に打ち込んでいた場合、部活を引退するまで十分に学習時間が取れなかったお子さまが多いのではないでしょうか。
中学3年生の夏からの受験対策は、学力と志望校のレベルにあまり差がなければ、十分に間に合います。ここでは、限られた時間を有効活用して勉強するポイントを解説します。
まずは地域の模試を受けて自分の学力レベルを把握する
入試対策を始める前に、まずは自分の学力と志望校合格に必要な学力の差を把握する必要があります。
学校の定期試験はあくまで学習の振り返りとして実施されるもので、入試に必要な学力がついているかを確認できるものではありません。自身の学力を客観的に知るためにも、まず地域で有名な模試を受験しましょう。
主に学習塾を通じて、地域ごとの模試が実施されています。
大阪なら「五ツ木」、愛知なら「全県模試」、埼玉なら「北辰テスト」、東京なら「Vもぎ」など、各地域の公立高校受験用の模試を受けてみることをおすすめします。
模試の結果を見て、自分がどのレベルにいるのか、志望校に合格するためにはあとどの程度成績を上げなければならないのかをチェックしておきましょう。
志望校を決定する
次に高校の偏差値と自分の実力を照らし合わせて、現実的な志望校を検討します。模試の結果をもとに学校や塾の三者面談で相談しながら、併願校なども具体的に決めていきましょう。
なお、志望校を決める際には、偏差値だけでなく自分の目標や希望する職業につながる学校かどうかを基準に考えることも大切です。
英数国を重点的に全科目の対策を行う
3年生の夏以降、本格的な入試対策の演習などが始まります。英語、数学、国語など配点の多い主要教科に重点をおきながら、理科や社会の学習も進めていきましょう。
受験直前の追い込み勉強法

受験直前には、苦手分野の最終確認、得意分野の強化、そして過去問演習に取り組みます。
過去問を繰り返し解くと、問題に慣れ、時間配分や出題傾向を把握できるというメリットがあります。限られた時間を無駄にしないよう、塾に通っている場合は塾と相談しながら、優先順位を決めて勉強しましょう。
受験勉強の効果的な計画の立て方
ここからは、受験勉強の計画の立て方を紹介していきます。計画は、以下の手順で作成しましょう。
入試制度について調べる
まずは、自分の受験する地域の入試制度について確認しておきましょう。公立高校入試は、地域によって内申点の割合や入試の方式・日程などが異なります。
たとえば、神奈川県立高校の入試では、内申点と学力検査(一般的な入学試験)に加え、神奈川県独自の試験である特色検査も実施されます。
公立高校の入試制度についての情報は各教育委員会が発表しています。また、各地域の学習塾が分かりやすく解説した記事もあります。塾の記事は読みやすいものが多いのでおすすめです。
一例として、神奈川県、千葉県、兵庫県の公立高校入試については、以下の記事が参考になるでしょう。
- 神奈川県『【2025年保存版】神奈川県公立高校入試のしくみ』
- 千葉県『【最新版】千葉県公立高校入試の仕組み』
- 兵庫県『【2025年度対応】兵庫県公立高校入試について徹底解説します』
志望校のレベルと現在の学力の差を把握する
学習計画を作成する際には、現在の学力と目指すレベルを比較し、その差を埋めるために何をすべきかを洗い出します。現在の学力を知るには、地域の模試または実力テストを受験するのがおすすめです。
模試は、自分の学力を客観的に把握し、志望校合格に向けた課題を見つけるために役立ちます。定期的に受験し、結果を分析して弱点を克服しましょう。志望校と同じ形式の模試を受けることで、入試本番の雰囲気をつかむ練習にもなります。
入試までの学習計画を作成する
模試の結果が返ってきたら、それをもとに合格に必要な学力をつけるための計画を立てていきます。入試日程から逆算して、余裕を持った計画を作成しましょう。
学習計画は、達成できる内容にすることが重要です。自分の生活に合わない無理なスケジュールは、予定通りに進まない可能性が高くなります。学校や部活を考慮したうえで計画を立て、改善しながら勉強を進めていきましょう。
また、定期的に実力テストや地域の模試を受験して、学力の定着状況を確認しましょう。定期的に学力をチェックすることで、計画を修正しやすくなります。
時間を効率的に使うために、日々のスケジュールを具体的に決めておきましょう。たとえば、定期テスト前はテスト範囲を優先し、それ以外の期間で受験対策を進めるという計画の立て方もあります。
部活動と勉強を両立するためには、限られた時間を最大限に活用することがポイントになります。疲れて自宅学習が難しい場合は、オフの日に塾で効率よく勉強するという方法もあります。
塾に通った方がいい?
一般的に塾に通う方が効率よく高校入試対策ができます。独学での対策ももちろん可能ですが、塾に通う場合に比べ情報収集が難しく、効率の面では塾に通う方がおすすめです。
特に部活動が忙しく、十分に学習時間が取れない場合は、塾で対策したほうがよいでしょう。
塾では過去問や模試を活用した入試本番の準備、定期テスト対策による内申点アップ、得意分野の強化と苦手分野の克服といったサポートが受けられるのが大きなメリットです。
また、最新のデータをもとにした進路指導により、志望校合格に向けた具体的な学習計画を立てられる点も魅力です。
高校入試の対策で塾に通うメリット
ここでは、塾に通う4つのメリットをご紹介します。
高校受験の対策で塾に通う4つのメリット
- 入試対策を効率的に行える
- 内申点アップのための対策ができる
- 最新のデータを活用した進路指導を受けられる
- 苦手科目の克服がしやすい
入試対策を効率的に行える
塾では、地域の公立高校入試の出題傾向に合わせた授業だけでなく、過去問や模試を活用した指導も受けられます。過去問に一人で取り組むのは難しいため、塾の力を借りられるのはメリットです。
内申点アップのための対策ができる
塾に通うと、内申点アップのための対策ができます。塾では、テスト範囲を網羅した問題演習やポイントを押さえた解説を行い、確実に点数を上げるサポートをしてもらえます。
最新のデータを活用した進路指導を受けられる
塾には、地域の高校入試に関する最新の情報が豊富に蓄積されています。これをもとに、志望校ごとの合格ラインや適切な目標点数を示してもらえるため、それに合わせた対策ができます。
学校では習わない応用問題などの対策もしてもらえるので、少しでも上を目指したいのであれば、ぜひ塾を検討してみてください。
苦手科目の克服がしやすい
苦手科目の克服のためには、どこでつまずいているのかを調べ、その時点まで戻って復習する必要がありますが、自力でつまずいているポイントを見つけるのはかなり難しいです。
そのため苦手科目がある場合は、その科目だけ塾で対策するのがおすすめです。一部の科目だけであれば塾費用を安く抑えることができますし、受験の相談もあわせて行えます。
塾選びのポイント
ここからは、塾選びの方法を4つのポイントで紹介します。

志望校や受験対策に合った指導があるか
まずは、塾の指導内容を確認します。公立高校入試の傾向に合わせた指導を行っているかどうかは重要なポイントです。また、進路指導を十分に行ってもらえるかも知っておきたいポイントです。
関連記事:都立高校受験に強いおすすめの塾4選!失敗しない塾選びのポイントも解説
関連記事:中学生におすすめの塾10選!料金相場や塾選びのポイントも解説
学校や部活と両立できるか
塾は、学校の活動に支障がない範囲で通うようにしましょう。具体的には部活の後でも間に合うかどうか、帰宅が遅くなりすぎないかなどを考慮します。睡眠時間を無理に削って学校の授業で寝てしまっては本末転倒です。
費用が妥当で納得できるか
授業料が予算内であるだけでなく、その内容が費用に見合う価値があるかを見極める必要があります。授業内容、模試の頻度、自習室の利用可否なども含めて、総合的に判断することが大切です。
授業料が安く設定されていても、季節講習費用や設備費などの追加料金で結果的に高くなるケースも多いため、必ず年間にかかる費用を確認しましょう。
関連記事:中学生の塾の料金はいくらかかる?平均費用や月謝の相場を知る
関連記事:子供の塾代ってどれくらい?高校受験の塾代の相場について
信頼できる合格実績があるか
合格実績は、指導力を判断するための指標の一つです。可能であれば、過去3年分くらいのデータを調べると、どのような学校に強いのかが見えてきます。志望校が決まっている場合は、その学校の合格者数の多い塾を選ぶのもよい方法です。
ただし大手塾の場合、全国の教室の合格実績をまとめて出しているケースも多いため、近くの校舎の合格実績を確認するようにしましょう。サイト上で公開されていない場合は、体験授業や面談で質問しましょう。
まとめ:今日からできる受験勉強の第一歩
この記事では、高校受験の対策を始めるおすすめの時期のほか、学習計画の立て方や勉強法などを解説しました。高校受験の対策は、早く始めるほど志望校合格に近づきやすくなります。塾の検討や志望校選びなど、今日できることから始めてください。
※本記事に掲載している情報は記事執筆時点のものです。料金・キャンペーンなどの最新情報は各教室にお問い合わせください。