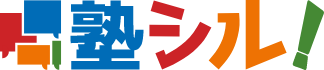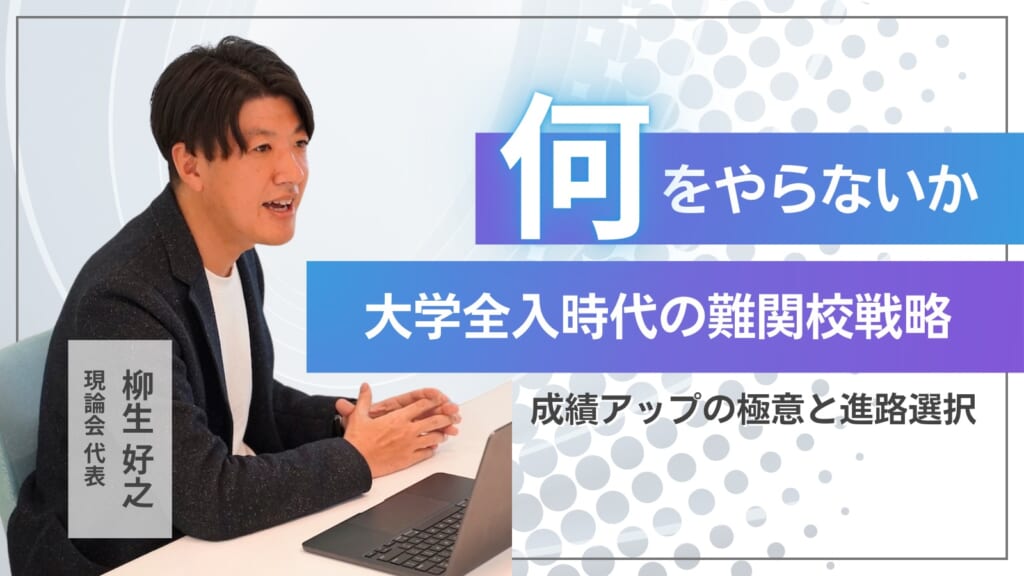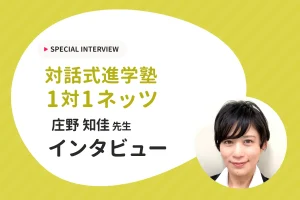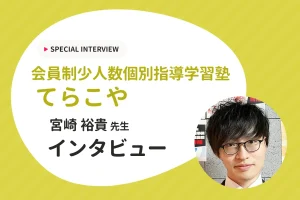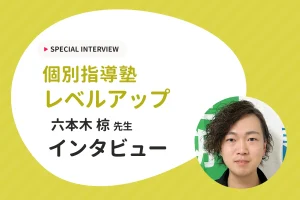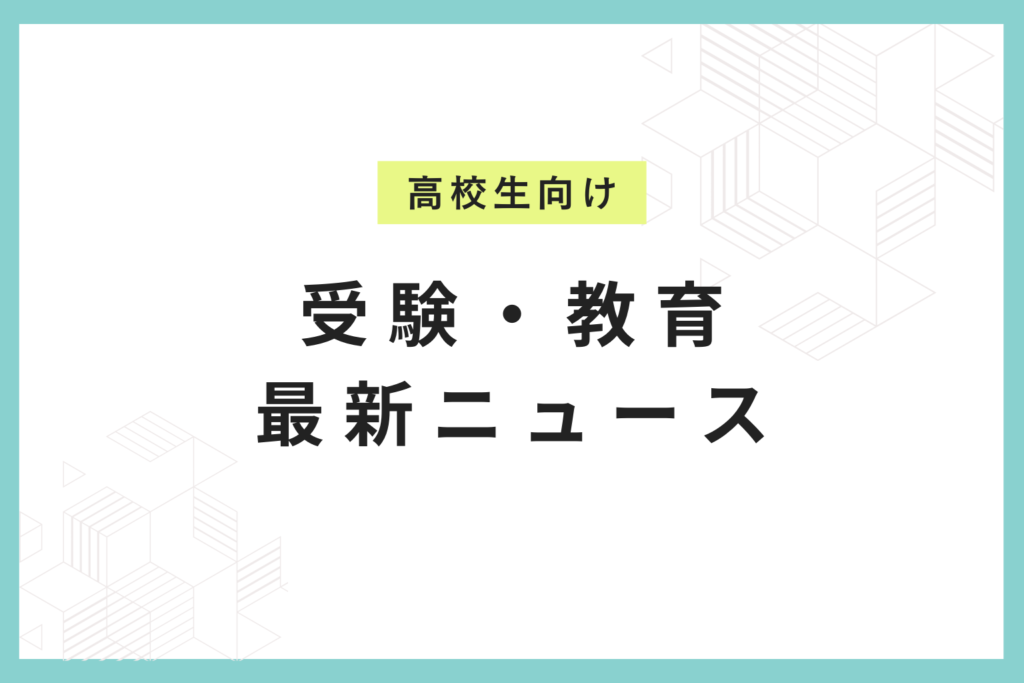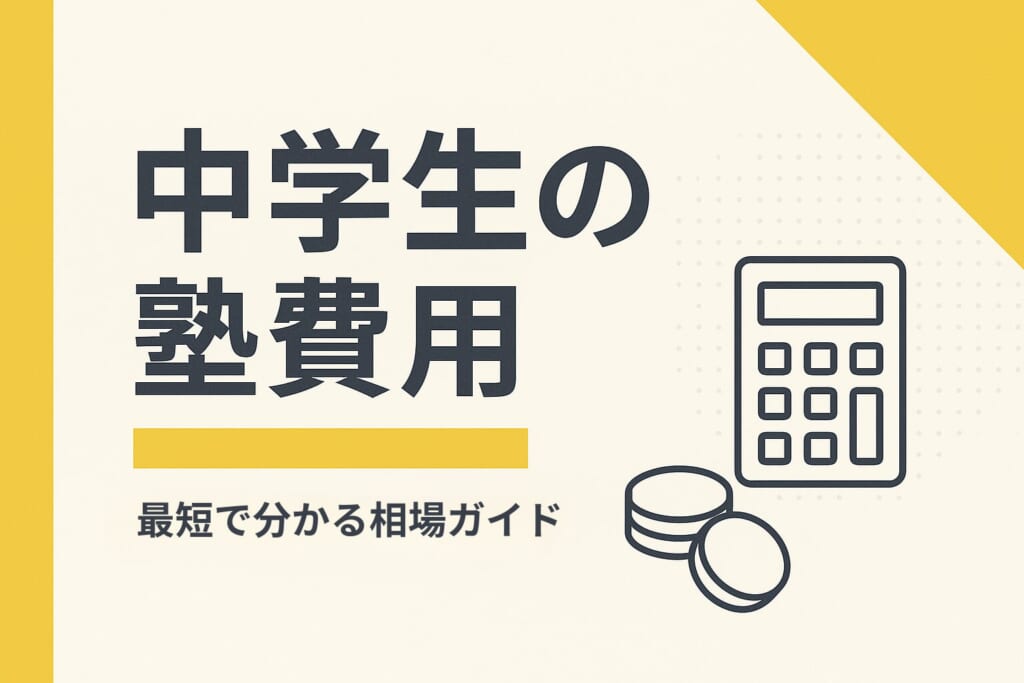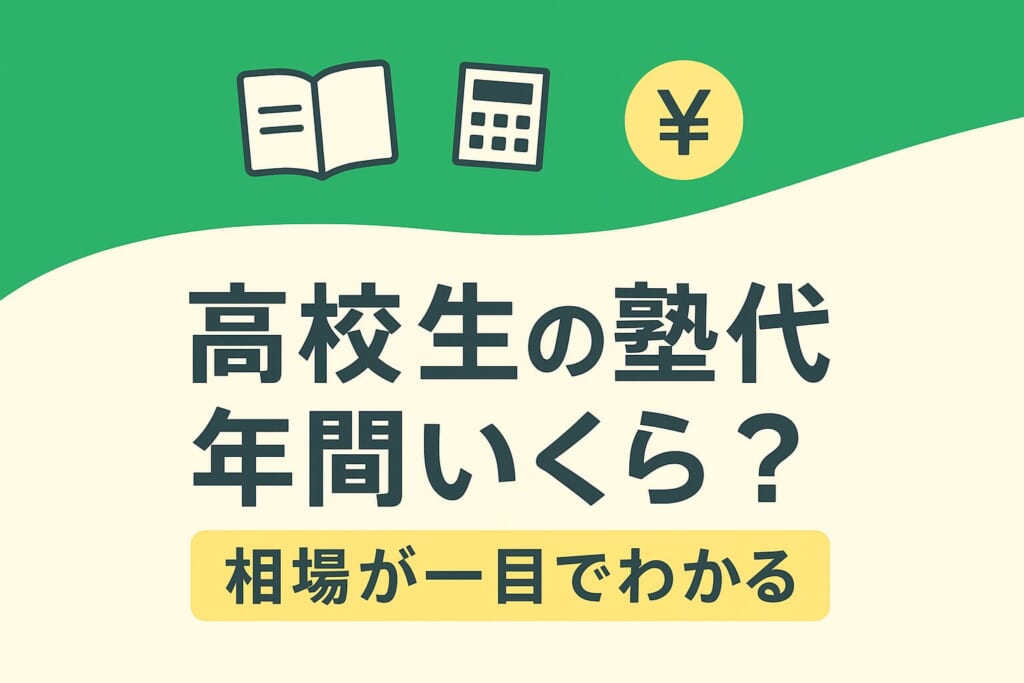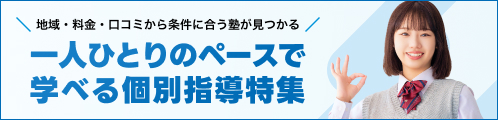大学入試の競争は年々変化しています。少子化が進む一方で、難関大学の人気は衰えることなく、むしろ「逆転合格」の事例が増えることで志望者は集中する傾向にあります。今回は、全国48校舎を展開する難関大受験専門塾「現論会」の柳生代表に、受験事情の最新動向や効率的な勉強法、そして総合型選抜の未来について詳しくお話をうかがいました。大学選びに悩む保護者の方々に、ぜひ参考にしていただきたい内容です。
今回お話をうかがった先生

柳生 好之(やぎゅう よしゆき)
早稲田大学第一文学部総合人文学科日本文学専修卒業。リクルート「スタディサプリ」現代文講師。難関大受験専門塾「現論会」代表。
インタビュアー

古岡 秀士(ふるおか ひでし)
「塾シル」を運営する株式会社ユナイトプロジェクトの代表取締役社長。2012年に青山学院大学大学院を卒業し、医療系ポータルサイトの営業を経て独立。塾シルは全国で13,000教室以上の学習塾を掲載している。
「大学全入時代」でも維持される難関大のブランド価値
——今回は「激化する大学受験について」というテーマで株式会社言楽舎の柳生代表にお越しいただきました。まずは柳生代表の自己紹介をお願いします。
私は長らく塾・予備校講師をやっておりまして、今はリクルートの「スタディサプリ」を中心に授業を担当しています。参考書の執筆のご依頼も多く、これまで27冊、50万部の本を世に送り出してきました。『ゼロから覚醒 はじめよう現代文』はベストセラーになっていて、代表作と言えます。
一方で、難関大受験専門塾「現論会」という学習塾も運営して、フランチャイズ展開も含めて日本全国に校舎を出しています。
——関東を中心に全国展開されているんですね。オンラインも始められたと聞いています。現在の校舎数はどのくらいですか?
今年(2025年)の春に48校舎になる予定です。全都道府県に出していき、ゆくゆくは日本一の大学受験ブランドを作りたいと思っています。
——野心的な目標ですね!それでは本題に入りたいと思います。今回のテーマである「激化する大学受験」について、柳生代表から見た現状をお話しいただけますか?
まず受験者に関しては、いわゆる「私大バブル」と言われていた90年代前半をピークに年々減っています。今回の共通テストも受験者はあまり多くいませんでした。少子化で今後ますます受験者数が減っていくことは確実です。
しかし「大学全入時代」といわれる中にあっても、大学側はブランド力を維持するために簡単に生徒を入れてはいません。当塾が専門にしている難関大学に限れば、昔と比べても合格の難易度は変わっていません。
——なるほど。少子化になろうと難関大学は「難関」であり続けるということですね。大学側はどのような工夫でブランド価値を維持しているのでしょうか?
まずは定員を絞ってきています。たとえば一昔前は1000人が定員だった学部を600人に減らせば、その分入るのが難しくなります。当然、偏差値は高いまま保たれます。「偏差値が高い」だけでも、一つのブランディングになるので、ブランド維持のために定員を減らすことはよくあります。
また以前は、早稲田大学や慶應大学などの難関私立大学では、東大などのより難関校への「流れ(=歩留率)」を見込み、定員1000人の学部に対して1500人程度の合格者を出していました。これにより追加合格や補欠合格の枠も広く確保されていました。
しかし、この慣行に対して文部科学省から定員超過に関する厳格な指導が入り、大学は合格者数を抑制するようになりました。つまり、定員に近い数しか合格者を出さなくなり、追加合格や補欠合格の枠も減少したのです。
その結果、一時期は合格がより難しくなりました(合格総数が減少したため)。現在はその厳格な定員管理がやや緩和されているものの、以前のような大幅な定員超過は行われなくなり、この合格者数の調整も難関校のブランド維持に寄与しています。
総合型選抜の採用が増えている理由とは?
——その規制がなくなっても難関大は難関であり続けているのはなぜですか?
はい、たしかに最近はなくなってきたんです。では、どういうふうに難易度を維持しているかというと、総合型選抜の入学枠を増やしているんです。入学者を確実に押さえられるからです。早慶は総合型選抜枠を増やしていて、一般入試の入学枠がどんどん少なくなっています。
話をまとめると、大学受験者数が減れば入学は簡単になると思われがちですが、難関大は狭き門であることは変わらず、難関というブランドを維持するための工夫をしています。いわゆる大学全入時代になっても人気大学に限っては入学の難易度は下がっていません。
—— なるほど。総合型選抜の増加は受験生にとって大きな変化ですね。また近年では共通テストの導入もありました。この共通テストについてはどうお考えですか?
共通テストは、実はひと悶着ありました。共通テストが導入された2021年は大きな変化が見えたのですが、今年の共通テストはいくつかの科目でセンター試験に回帰しています。実はセンターのままで十分思考力は問えていたんじゃないかという説もあります(笑)。
——柳生代表は国語の現代文の専門家としても知られていますが、国語の試験で特に変化を感じる点はありますか?
国語の試験では、大問が1個増えたのが大きな変化です。以前は評論文・小説文・古文・漢文の4題の構成でしたが、最近は評論文・小説文に「実用文」が加わり、古文・漢文と合わせて5題構成になったのです。
この実用文はセンター試験の時代にはなかったジャンルで、新しく見えるのですが、実際には評論文と小説文は完全にセンター試験に戻っています。センター試験の簡易版をイメージするとわかりやすいかと思います。文科省の試行錯誤の跡が見えます。
——共通テストは結局センター試験に戻りつつあるということですね。
逆転合格者は増加している?
最近では「自学自習」という言葉も聞かれるようになりました。それでも子どもたちは塾に行った方がいいとお考えですか?
おっしゃる通りです。自学自習というワードも流行ってきて、塾に行かない子も出てきています。そういう層も確かにいますが、ほとんどの方は塾に通った方が結果は出やすいと思います。これはポジショントークではありません。
というのも細かく見ていくと、勉強のやり方が上手い子と下手な子で大きな差があることがわかりました。自習をするにしても、勉強のやり方が上手い人は、同じ教材、同じ時間でもどんどん成績を上げていき、逆に勉強のやり方があんまりうまくない生徒は、同じ条件でもまったく成果が出ないことはよくあります。勉強のやり方にフォーカスして塾を選ぶのが、これからのトレンドになっていきます。
——勉強の「やり方」を教えてくれる塾が重要なことは想像できますが、入試は出題範囲が決まっていますよね。その中でもやり方は大きく変わるものなのでしょうか?
難関大学ーー関東であれば早慶やGMARCH、関西だと関関同立と言われる大学群ーーに、実は逆転合格で受かっている人が多数いることがわかってきたのです。
以前は情報が少なく「あの大学に行くのってもともと地頭がいい人でしょ」みたいなイメージをみんなが持っていたと思いますが、SNSの時代になって「偏差値38からでも難関大に合格しました」という人の声が容易に届くようになっています。情報が開かれた時代ならではのことだと思います。
——柳生代表ご自身も逆転合格の経験があるとうかがっています。
はい。何を隠そう私も偏差値38から早稲田に行き(笑)、SNSでそのエピソードを積極的に発信しています。以前はそんな話ってなかなかリアルに聞かなかったはずです。
私が講師を始めた20年前は、教室でそんな話をしたら生徒がびっくりしてくれましたが、最近の子は「よく聞く話ですよね」ぐらいで大してウケません(笑)。逆転合格が珍しくはなくなっているからです。「ビリギャル」なんかもそうですよね。短期間で偏差値を上げるノウハウが確立されつつあります。
——SNSやネットの普及で「逆転合格」のノウハウが広く知れ渡るようになったのですね。
そういったエピソードが巷にゴロゴロ転がっていることに、みんな気づいています。以前は塾予備校の関係者だけが知っている情報でした。SNS時代の特徴ですね。昨今は現状の学力が低くても難関大を目指そうという気風が高まっています。これが難関大学の人気の集中へとつながっています。
私も自分自身が偏差値38から早稲田大学に受かったものですから「誰でも早稲田受かるぞ」と授業中も煽ったりするので、「自分も早稲田を目指します!」という子がいっぱいあふれかえるわけです。そうするとやっぱり相変わらず難関大は難関大ということになります。
——ある意味、柳生先生のような方が難関大学の人気を作っているとも言えますね(笑)。一方で中堅大学はどのような戦略を取っているのでしょうか?
中堅校のブランドの作り方は独特です。たとえば駅伝や、サッカー、野球などのスポーツ関連で有名になる戦略もあります。他には、就職先がいいとか、面倒見がいいというようなところでアピールするような大学もあります。
関東では日東駒専という大学群はそういう独自のアピールに力を入れています。
効率重視の受験勉強術~高2夏までに始める早慶対策
——なるほど。マーケティング戦略も重要なんですね。とはいえ、入学時に求められるのは学力だったり内申点であることは変わりません。受験勉強の中で特に過去問の重要性についてはどうお考えですか?
過去問は、合格への最短ルートを歩くのに絶対必要なツールです。それでも使い方を知らない子に「過去問をやりましょう」と言ってもうまくはいきません。過去問の分析がポイントになります。当塾でも過去問に入る前の最低限必要な知識というものをあらかじめ定めておきます。各科目において一定レベルを定め、「これだけやったら過去問入っていいですよ」と決めておき、スムーズに過去問に入るように指導しています。
——早い段階から過去問に取り組むメリットはどういった点にありますか?
生の講義を中心とした従来の塾予備校では、出題範囲が終わるのが入試の直前になってしまいます。今は映像授業と参考書が充実しているので、最低限これだけ押さえておけば過去問に入れるよという状態が夏前に作れるようになっています。
——早めに過去問に入るのであれば、志望校選びも早期に始める必要がありますね。
おっしゃる通りです。対策する大学を決めないことには逆算が成り立たないので、早期に志望校を決めることが重要になります。
ところが、これができない子が多いのです。入塾時に「どこの大学行きたいの?」と訊いても、まだわからないと答える子が実は多いのです。そのような場合、当塾は難関大受験専門塾なので、たとえば私立文系だったら早稲田大学、国公立だったら東京大学と設定して、何をどのようにするかをあらかじめ決めて、これだけやれば過去問に入れるよと提示した上で進めてもらいます。
成績アップのカギは「何をやらないか」の選択にあり
——志望校を早めに決めて、逆算で参考書や映像授業で進めていくことは理解しました。参考書は昔から使われていますが、質が変わったり、勉強の効率も変化しているのでしょうか?
最近の参考書は、入試をしっかり研究した先生が作っているので、これだけあれば十分というふうにコンパクトになっています。無駄な勉強が本当に減っています。
——一般的に学習塾の先生たちは参考書についても把握して、最適な勉強法を提案できているのでしょうか?
現場の先生が情報を持っているかと言われたら、正直微妙ですね。塾予備校の先生は自分の授業がいいと思っているので、「あの参考書は駄目だよ」と古い知識で批判的に話すことはよくあります。実際に生徒から「この参考書は良くないと言われたけど、このまま使っても大丈夫でしょうか?」と相談を受けることもあります。
意外と見落とされているのですが、参考書の知識が本当にあるのは直近で受験を終えた大学生です。現論会では参考書の研究チームやコーチングスタッフには、直近で難関大に合格した大学生を採用しています。実際に自分で使って最新の入試問題も経験しているので、参考書に詳しいのは彼らなのです。
——それは興味深いお話です。先日私の知り合いの話で、お父さんが自分が学生時代に使っていた参考書を子どもに買い与えて混乱させたという話がありました(笑)。
よく聞く話です(笑)。
そのお父さんが最新の入試情報を研究しているわけではないでしょうから、学校の宿題のバランスも見ずに、自分の経験のみで参考書を買い与えるのはあまりよくないですね。おおむね参考書は新しいものの方が入試には向いています。
——目指す大学のレベルによって使う参考書も準備期間も変わってきますね。
たとえば早慶に行きたいなら、最低でも高2の夏には対策を始める。東大に行きたいなら、高1の頭から始める必要があります。一定の学力があり、MARCH志望であれば、高3の頭でも間に合うかと思います。しかし実際は始めるのが遅くて苦労している子が多いのです。
——SNSなどで「高3の夏からでも間に合う」という情報を見て、勘違いしている生徒さんも多いのではないでしょうか?
先ほどの情報の話にも通じますが、どんな大学でも高3の夏から間に合うと勘違いする子もいるかもしれません。SNSでそういう情報を見ることがあるのかもしれません。
しかし、夏から間に合わせるには、学校の授業中に内職をしたり、学校の授業を「自主休校」できる人たちが言っているわけであって、学校に真面目に通っていたら難しいと思います。
——情報を鵜呑みにするのではなく、自分の状況に合わせた判断が必要ですね。
ひとの情報に踊らされないで、自分の学力に応じて今何をやるべきかを見極めてほしいですね。そこはプロの目を頼っていただきたいです。状況によっては準備期間は変わってきますから、塾に相談した方がいいと思います。
スマホ・SNS対策~受験生の集中力を高める環境づくり
——参考書の活用については理解しました。つづいて映像授業の活用についても教えてください。
対面の授業がメインの学習塾に比べると、映像授業の方が「効率がいい」というのは定着しています。単純に1年分の授業を3ヶ月で見ることができるので、市場の評価を得て発展してきました。東進ハイスクールを代表例として、集団授業から映像授業へと変化した歴史もあります。東進ハイスクールでは集団授業と映像授業を両方実施していた時期があり、入試の結果は映像授業を受けていた生徒たちの方が良かったという実例もあります。
——柳生先生も出講するスタディサプリなどのオンライン学習サービスの台頭もその流れの一つですね。
コロナ禍の少し前からスタディサプリが支持され、特にコロナの時は一気に浸透しました。それまではトップ講師の映像授業を受けるには高額の予備校に通わないと受けられませんでした。
しかし、インフラの拡張などと相まって手持ちのスマートフォンで定額見放題という時代に移行しました。スタディサプリが登場した当初は批判も多かったのですが、テクノロジーの進化、ビジネスモデルの進化には抗えません。あらゆる分野で「サブスク」が当たり前になったのは必然的なことだと思います。
—— コロナ禍でそれが一気に加速したんですね。
教育業界には保守的な考えの方も多くいて、「スマホで勉強なんかできるわけない」という意見の方が一定数いました。これを圧倒的に変えたのがコロナ禍です。何かを学ぶ、人に教わるために外出することが避けられ、自宅で学べるスタディサプリが爆発的に伸びました。しかし、そのときにあらためて「授業はこれでいいんじゃないの?」とみんな気づいてしまったんです。
——しかし授業が見放題になっても、それをうまく活用できない生徒も多いのではないですか?
まさにそこです。私自身もスタディサプリに参加して、学生が受けたいものを定額で提供できる機会に参画できたことを光栄に思います。しかし、自分で効率よく学べる人が実はごくわずかであることも意識しています。
選択肢が多すぎて、自分に合う授業がどれかわからない。気づけば自分が得意な科目ばかり見てしまう、そんな生徒も出てきます。これがサブスクの一番の特徴です。
——つまり情報や教材が豊富になった時代だからこそ、選別や戦略が重要になってきたということですね。
一昔前は予備校のトップ講師は都市部の校舎しかいませんでした。その後映像でネットにつながる地方の校舎に届けるように変わりました。それがサービスとして成立した時代があったのですが、ネットのインフラが拡張・高速化され、サブスクが当たり前になると自宅でいくらでも良質なコンテンツに触れることができます。また、従来から主流である参考書も活用されています。私自身も、たくさんの参考書を書かせていただきましたが、参考書の質・量ともに今ほど充実している時代はありません。まさに大参考書時代と言われるような時代になっています。
映像授業にしても参考書にしても学ぶツールがありすぎて選択に困るというのが今の問題です。昔はツールがなさすぎて、授業や映像のために塾に行ったのです。今はありすぎて困る時代になったので、塾も発想の転換をして「何をやらないで済ますか」をしっかりとアドバイスすることが求められるようになっています。
——なるほど、「何をしないか」が重要なポイントなんですね。現論会はそこに着目したサービスを提供されているわけですか?
その通りです。現論会は「最も効率よく大学受験を乗り切る」をテーマにしています。キャッチコピーは「最小の努力で最大の結果を」としています。生徒に対して何をやらないで済ますかを自信を持って言えるにはプロを育成する必要があります。
受験で培われる「グリット」~社会で活きる非認知能力の育成
——受験は勉強面のスキルだけでなく、精神面も鍛えられると思います。そういった意味では受験勉強によってどんな力が培われていくと思いますか?
私は国語の指導を担当していて、国語の読解力と書く力は社会に出てからも十分役に立つと思います。意外かもしれませんが、数学も役立ちます。学生時代にしっかり勉強する意義はあります。
とはいえ、受験が終わったら使わない知識もいっぱいあるわけです。「それでも勉強する意味があるのか?」と思われる方も多いですし、その気持ちはわかります。しかし、いまご質問いただいた通りで、計画を立てたり集中する力は非認知能力の中でも、やり抜く力とか「グリット」と呼ばれ、最近評価されています。難関大受験を乗り切った子には、多少つらくてもやり切れるだけの粘り強さが身についているのです。
——「グリット」は最近注目されている非認知能力ですね。受験勉強はまさにそれを養う機会になるわけですね。
その通りです。仕事を楽しんでいる人でも、実際によく見てみると楽しい時間なんて3%ぐらいで、残りの97%ぐらいは辛抱強さが求められていますよね。
たとえば私の場合、新しい本が出版された時はめちゃくちゃ嬉しいです。なのですが、書いてる瞬間は苦しみしかありません。「なんでこんな仕事を引き受けちゃったんだろう?」と後悔することも多いのです(笑)。
3%の嬉しい瞬間を得るために97%のつらい時間があったとしても、受験勉強でやり抜く力を身につけた子は、大人になってもがんばれます。おもしろい授業を受けたり、問題が解けたり楽しい瞬間はありますが、楽しくない、つらい時間の方が圧倒的に長いわけです。受験は非認知能力の育成には良い機会です。
——物事をやり抜くには、集中できる環境だったり、やること以外のストレスをなくすには工夫がいると思います。受験期の子どもたちのメンタルケアについてアドバイスをいただけますか?
今の時代は子どもに対してストレスが多いですね。スマホとSNSの影響が大きいと思います。私が受験生の頃はスマホもSNSもありませんでした。当時は携帯電話とかPHSはありましたが、受験生のときに解約しました。今になって受験がうまくいった秘訣であったなと振り返ります。
周りの生徒たちが気を取られてる間も勉強に集中できました。今の子たちはスマホ、SNSとの向き合い方に気をつけた方がいいでしょう。スマホを持たないことが一番いいかなと思います。
——とはいえスタディサプリなどはスマホで使うものですよね。そこが難しいところですが……
そうなんです! これは難しいところです。ですのでスタディサプリのアプリだけ入れておいて、SNS関連のアプリは全部削除することを推奨します。SNSはストレスの元凶なので、受かるまでは絶対入れないぐらいで良いと思います。
私もSNSを利用していて、受験生の利用者は減っているのではないかという気がします。少し前まではX(旧Twitter)に受験生がいっぱいいましたが、最近はそうでもありません。私のSNSの発信は、保護者向けの内容に切り替えています。受験生はなるべくSNSには触れて欲しくないですね。親御さんたちもそこは注意して欲しいですね。
探究学習と総合型選抜が求める力を養うには?
——最後に、これからの教育のトレンドについてお聞かせください。入試改革の時期から「探究学習」が注目ワードとして取り上げられています。これは大学入試にどう影響していくでしょうか?
探究学習について文科省は試行錯誤しているように思います。総合型選抜の枠がどんどん増えていることは周知の通りです。従来の総合型選抜の対策といえば、一般入試の勉強と並行しながら小論文の対策をする。志望理由書、小論文、面接は、その場の判断で対応するというものでした。
受かる経路を増やすために総合型選抜を検討する生徒もいますが、本来のあるべき姿ではありません。総合型選抜がうまく合うのは、解決すべき社会課題が見えている人、それに向けて既に動き出している人です。どんな社会課題でもいいのですが、課題に対して自分はこういうアプローチをしていますと言える人です。そこでおすすめしたいのは起業です。
——高校生で起業ですか!? 斬新な視点ですね!
「社会の問題を解決するためのサービスを作りました。会社を立ち上げて運営しています」という生徒が総合型選抜を受ければ、さほど苦労せず合格すると思います。
起業家を育成する過程で、「探究」活動は必要になります。今は何が問題なんだろうと考えるのが大前提ですよね。高い偏差値の大学に行き、大手企業にサラリーマンとして就職する以外の未来も見ていく方がいいですね。
起業家とは世の中の問題を見つけて解決するサービスを生み出す人です。問題発見・問題解決の思考がないと起業家にはなれません。この問題発見・問題解決は、総合型選抜をやる上でものすごく重要な考え方になっているのです。志望理由書に関しても小論文に関しても、そういう思考ができている人物かが問われます。
——それでも起業となると敷居が高く感じる人も多いと思います。
会社設立は20数万円でできますし、別に会社じゃなくても個人事業主でも全然問題ありません。ビジネスにするのが難しいジャンルであれば、まずはボランティアから始めるのもありです。
問題発見・問題解決の思考がどれぐらいできるのかが志望理由書にも、小論文、面接にも生きていきます。未来を考えて行動することが受験にもつながっていきます。
——子どもの進路に悩んでいる保護者へのメッセージをお願いします。
かつては一般入試が大多数で学校推薦選抜が若干あるという形でした。今は大学に合格するルートはたくさんあります。お子さんに受験を経験させる場合、どの段階がベストなのかをよく見極めることが重要です。
中学で受験するのか高校で受験するのか。また、大学には進学すべきなのか。お子さんの特質、やりたいことをよく見極めた上で、どこで勝負するのかを決めてもらいたいですね。
見つからないのであれば、スポーツでもなんでも良いのですが、興味関心があるものをしっかりとやらせてあげてください。いずれお子さんが自分で自分の道を選ぶときが来るので、それを辛抱強く待っていただきたいなと思います。
——大学受験の現状と未来について、大変参考になる内容でした。今日は貴重なお話をありがとうございました。
取材協力:現論会(運営:株式会社言楽舎)
※本記事に掲載している情報は記事執筆時点のものです。料金・キャンペーンなどの最新情報は各教室にお問い合わせください。