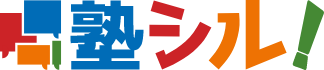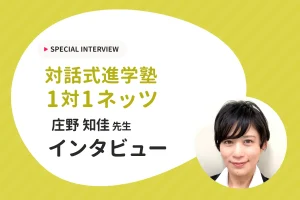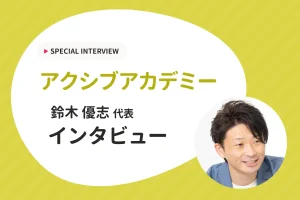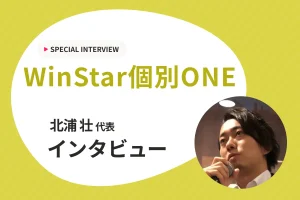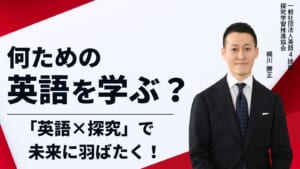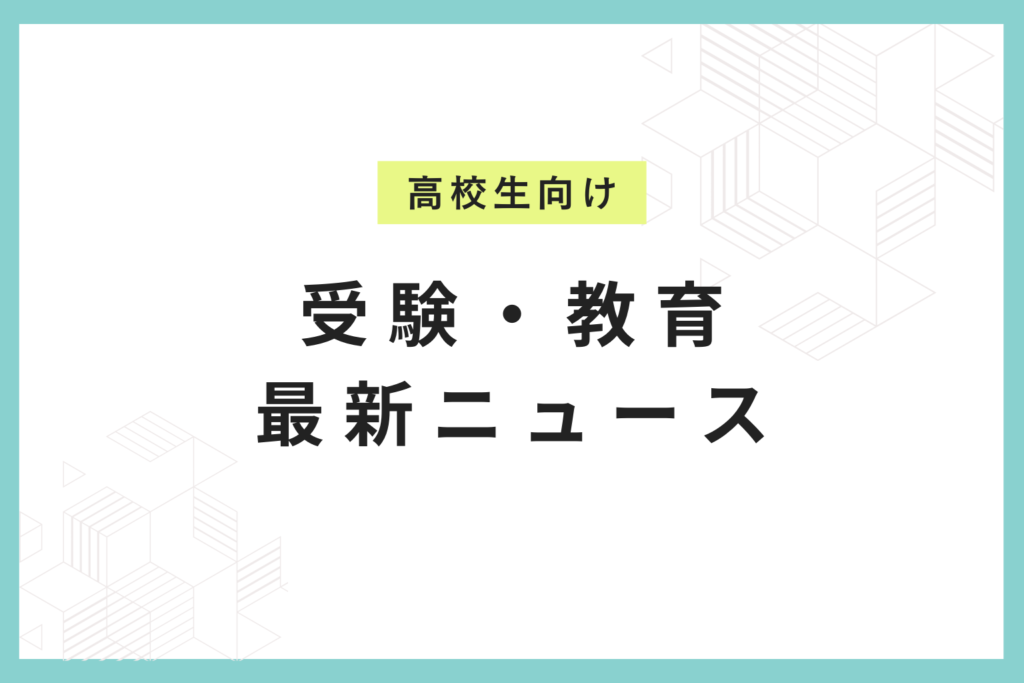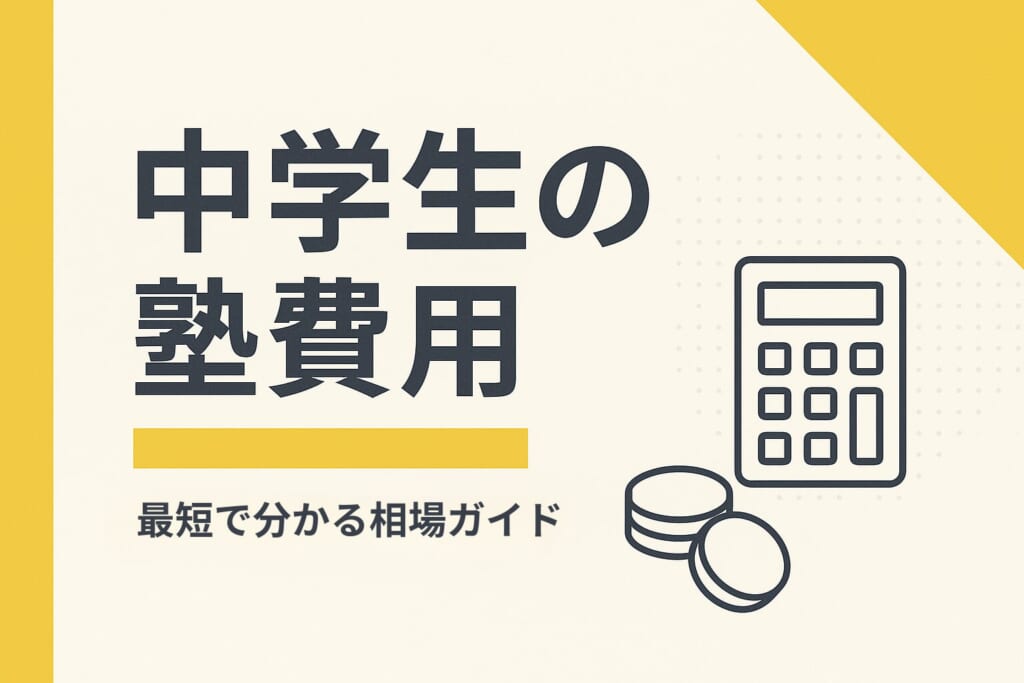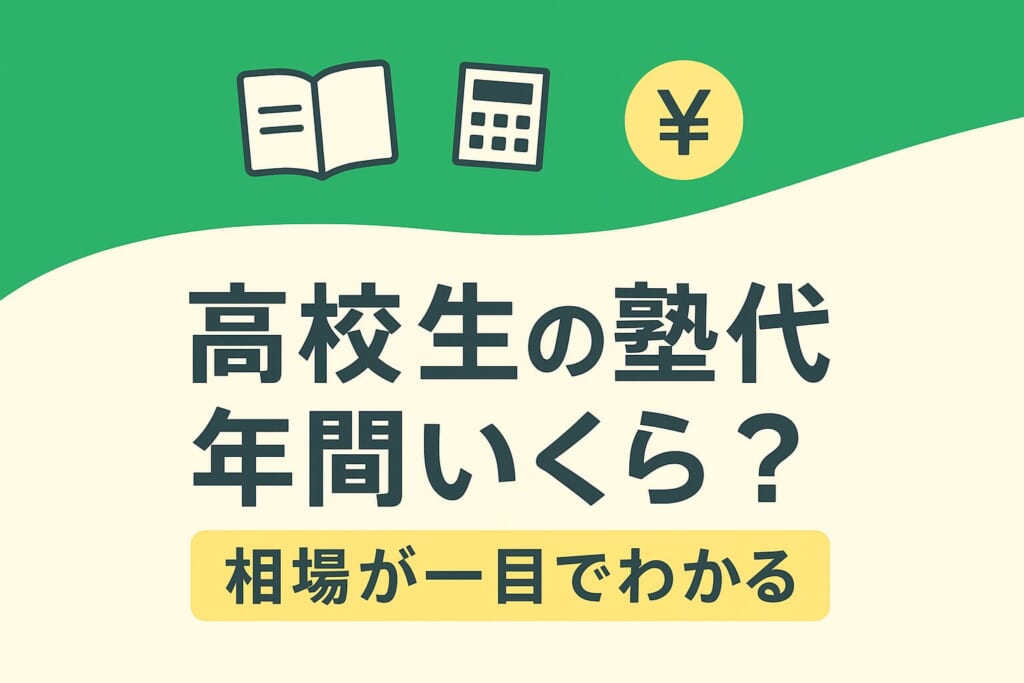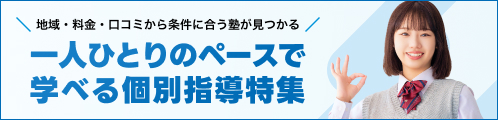「天才は育てられる」—— この大胆な仮説のもと、脳科学の知見を活用した独自の教育メソッドを展開する「りんご塾」が話題を呼んでいます。滋賀県の一地方都市から始まり、いまや算数オリンピックで全国レベルの実績を誇る同塾。その革新的な指導法と、子どもの才能を引き出すアプローチについて、運営会社・城南進学研究社の千島氏に詳しくうかがいました。
今回お話を伺った先生

千島 克哉(ちしま かつや)
株式会社城南進学研究社取締役副社長COO、公益社団法人全国学習塾協会常任理事、一般社団法人教育アライアンスネットワーク理事兼事務局長。 乳幼児から社会人まで幅広い層を対象に教育事業を手掛ける。「たくましい知性、しなやかな感性を育む能力開発のリーディングカンパニーへ」をヴィジョンに掲げ、日々、子どもたちの未来のために献身的に活動している。
インタビュアー

古岡秀士(ふるおか ひでし)
「塾シル」を運営する株式会社ユナイトプロジェクトの代表取締役社長。2012年に青山学院大学大学院を卒業し、医療系ポータルサイトの営業を経て独立。塾シルは全国で13,000教室以上の学習塾を掲載している。
——本日はよろしくお願いします。今回は「子どもを天才に育てるには」というテーマでお話をうかがうのですが、そもそも「天才とは何なのか」という部分から教えてください。
天才というと「先天的に才能に恵まれた人」というのが一般的な認識ですが、私が今回テーマに掲げる天才というのは、その先天的な話ではなく、秀才以上というイメージでお聞きいただけると理解しやすいかもしれません。
秀才はどんな定義なのかというと、努力によって優れた成績を収めるとか、努力によって能力が開花すると言われています。この秀才を後天的な要素でそれを超えていこう、それを天才と言っています。
——なるほど。では「天才」は育てることが可能だとお考えなのですね?
はい、「天才>秀才」という定義であれば、一般の人々とは異なるレベルでの創造性や知的能力を発揮する能力を育てることはできるのではないかと考えています。
——その考えの根拠となる研究や知見などはありますか?
中室牧子さんという慶応義塾大学の教授で教育経済学者が書いた本がベストセラーになりました。その方が最近出した本の中で、興味深い指摘をしています。「これからの教育というのは、根拠なき精神論や根性論に立脚するのではなくて、脳の仕組みや人間心理などサイエンスの視点に立った教育が必要だろう」という考えです。
天才の定義を再考~秀才を超える後天的な能力開発とは
——科学的なアプローチが重要というわけですね。そこで気になるのですが、教育開始の適切な時期について、専門家としてどうお考えでしょうか?
脳科学の観点から申し上げれば、脳神経細胞が脳内に溢れている0歳から始めるべき! と断言いたします。実際に私たちの「Kubotaのうけん」では脳が活発に成長する0歳~3歳までの時期に良質な刺激を豊富に与えて育脳を促進するレッスンをしています。
脳は生まれた直後から3~4歳までに大きく成長し5歳までには成人に85%まで発達し終えてしまいます。月齢や年齢により脳内で発達する部位が異なるため、いつから開始をするのが良いという表現をすることは難しいのですが、できる限り早い段階からの「育み」をお勧めします。
——脳科学的な観点からも、早期教育の意義について教えていただけますか?
私たちの「Kubotaのうけん」では、脳の前頭前野を鍛えることに注目しています。世界的な脳科学の権威である久保田競先生の監修のもと、科学的なアプローチを行っています。
生まれたときの脳神経細胞は140億個あり、これは個人差がありません。ただし毎日10万から20万個が死滅していきます。体の他の部分の細胞とは性質が異なり、脳の神経細胞は増えることはありません。では、どのように脳は発達していくのでしょうか? 脳の発達とは、神経細胞同士のつなぎ目であるシナプスが増えることで、神経回路が密になることをいいます。
「見る・聞く・触る」といった刺激や体験を重ねることで、脳の中で脳神経細胞同士がくっつき、回路ができていきます。そしてその回路同士が、またシナプスで結ばれていく。これらの回路が前頭前野に集まっていくことで、脳が発達していくんです。回路を密にすることで脳は発達し大きく育ちます。脳神経細胞の発達という科学的な観点からも早い段階での育みには大きな意味があるといえます。
ちなみに幼児教育の分野では、ノーベル経済学賞のジェームズ・ヘックマンの研究がよく知られています。「幼児教育の経済学」の中で、幼少期に適切な教育を受けた子どもは、将来の教育投資効果が高いということも示されています。
早期教育のリスクは乗り越えられる
——早期教育のリスクについて、具体的にはどのようなことが考えられますか?
一番懸念されるのは、子どもの声が適切に拾えないことです。幼い子どもはボキャブラリーが限られていて、たとえば「嫌だ」という気持ちを適切に表現できません。そのため、親が一方的に「これが良いはず」と思い込んでしまう危険性があるとは思います。
親は熱心なあまり、一つの方向に向かってアクセルを踏み続けてしまいがちです。教育熱心なのはいいのですが、それが教育虐待に一歩踏み込んでしまう危険性があります。年長の子どもなら「嫌だ」と意思表示できますが、より小さな子どもにはそれが難しい。親がアクセサリー的に子どもを扱ってしまうことさえあります。これは早期教育における最大の落とし穴かもしれません。
——そのようなことにならないためにどんな工夫が必要でしょうか?
まず大切なのは、ひとりひとりの子どもの発達段階や興味関心を尊重することです。プレッシャーをかけず、他人と比較せず、学ぶことそのものを楽しむという視点を持つことが重要です。何かできたら具体的に褒める。特にプロセスを重視して褒める。これは面倒くさく感じるかもしれませんが、とても大切なことです。承認欲求は大人でも子どもでも同じようにありますから。結果よりも、学びのプロセスを重視して褒めてあげることが大切です。
算数オリンピックで金メダル28名輩出。滋賀県から全国区へ
——昨年から御社が展開する「りんご塾」についてお話を聞かせてください。りんご塾では、どの年齢から受け入れていらっしゃるのでしょうか?
幼稚園の年中から始められますが、実際には年長から通われる方が多いです。受験が終わるのが埼玉9月、神奈川10月、東京11月なんです。そうすると11月ぐらいから、最初の大募集期間になります。天才にさせたいという親御さんがきますね。
——りんご塾の設立には、どのような背景があったのでしょうか?
滋賀県彦根市の会社が作ったのがりんご塾です。田邉さんという方が代表をやられているのですが、彦根市で算数を主体にした塾を開いて、毎年毎年、算数オリンピックのメダリストを出しているのです。
これが非常に興味深いところなのですが、滋賀県は47都道府県で一番学力レベル低く、彦根市は私立の小学校がないエリアなのです。その地域から、なぜ算数オリンピックのメダリストが毎年出ているのかを、不思議に思いご縁あって取材をさせていただき、最終的に一緒にりんご塾をやろうということになりました。
——他の学習塾とは異なる特徴があるということですが、りんご塾ならではの理念はありますか?
生徒ひとりひとりの発達段階に応じてレッスンを展開していきます。従来の塾は、学年に縛られていて、苦手克服に重きが置かれています。学年の枠内での難しい勉強はするのですが、学年を飛び越えてどんどん先へというものがないのです。
子どもは可能性の塊なので、可能性に火をつけるのです。幼少期の子どもたちに、大人が勝手に決めたルールの中で蓋を閉じてしまうのではなくて、才能を開花させる。それがりんご塾のユニークなところです。
算数オリンピックでしか得られない価値
——特に算数オリンピックに力を入れていらっしゃるそうですが、なぜ算数なのでしょうか?
算数というのは、世界共通の言語というか、世界共通で唯一競い合うことができる種目が算数です。田邉さんの考えでは、世界で競い合う算数オリンピックというのが最高の舞台で、その最高の舞台に子どもたちを参加させて支援したいと考えています。
おもしろいことに、受験と違って算数オリンピックには、合格・不合格という残酷な線引きがありません。だめなら、また挑戦すればいい。新たなチャレンジ精神や意欲の喚起みたいなものが、すぐにできる。だからこそ落ちこぼれることや、やる気をなくしてふてくされることがないのです。
「オリンピック」という言葉を聞いて知っている子どもたちは、算数オリンピックに出るんだということだけで、自己肯定感がめちゃくちゃ上がってくるんです。実際に友達に自慢げに話をしている光景をよく目にします。
——具体的にどのような指導をされているのでしょうか?
算数オリンピックを目指していく上での具体的な取り組みの前提としては、楽しく学ぶということです。それから飛び級です。これが合格をさせるためには絶対に必要です。算数オリンピックだからといって、勉強に追い込むとかいうことではなく、楽しんで飛び級をしていって、具体的な成功体験を積んでいくプロセスを大事にしています。
たとえば、算数検定や、思考力検定を受けていただきます。それから算数オリンピックの対策模試が、年4回あります。こういったものを受験していただいて、確実に成功体験を積んでいきます。このプロセスの頂点に算数オリンピックがあります。予選が6月、本戦が7月ですけど、この一連の流れが天才を育んでいくプロセスといえます。
——算数的思考力を育てることは、将来どのように役立つとお考えでしょうか?
これは時代の要請とも深く関係しています。僕が子どもの頃には、親から「読み・書き・そろばん」と言われました。でも今は、「数理・データサイエンス・AI」が、「読み・書き・そろばん」と並ぶスキルとして必須になってきているのです。
ソサイエティ5.0や第4次産業革命という言葉に象徴されるように、過去の延長線上に未来がないような時代になってきています。そこで武器になるのが、「数理・データサイエンス・AI」のような能力です。そしてその土台となるのが算数的思考力なんです。
例えば、企業の人事が採用時に求めたいスキルとして、問題の解決力、分析力、論理的思考力、情報処理能力などがあげられます。これらの土台になるのが算数的思考力です。大学受験でも数学の受験を必須とするという流れが出てきております。算数や数学が国富の源泉となるような社会に世界中が向かっているわけですから、これまで以上に算数的思考力が日常のあらゆる場面で活きてくるのではないでしょうか。
子どもが算数に夢中になる仕組みづくり
——小さな子どもを教えるに当たって気をつけていることはありますか?
田邉先生の教育モットーは「難しいことをやさしく、やさしいことをおもしろく、おもしろいことをより深く」なんです。80分の授業を三つのカテゴリーに分けています。
りんご塾の授業は80分で低学年にとっては一見、長いように思われるかもしれません。でも、その80分を楽しく効果的に使うための工夫をほどこしています。まず一つ目が、パズルプリント。二つ目がりんご塾のテキスト。三つ目が積み木です。
パズルプリントは算数的な思考力を試すものです。単なるパズルではなくて、それを解くことにより、算数の核となる概念が自然と身につくような仕組みになっています。生徒はもう楽しくて、パズルプリントを夢中になってやります。
心理学的な工夫も取り入れていて、最初にパズルで楽しい、真ん中が勉強、そして最後にまた積み木で楽しい、です。これは初頭効果と期末効果という心理学の知見を活用しています。楽しいもので挟む「サンドイッチ方式」にしているんです。
積み木では空間把握能力を鍛えます。大きさ、高さ、奥行き、位置関係などを認識する力が遊びながら身につくのです。子どもは積み木に夢中になり帰りたがらないんです。むしろ、最後は親御さんが子どもの手を引っ張って帰るような状況が多く見られます。学びが楽しいものになっているという証でしょうね。
——りんご塾の具体的な成功事例を教えていただけますか?
最近の実績でいうと、城南進研全体で金メダル5名、銀銅メダル23名を出すことができました。金メダルというと、灘や開成のトップレベルと同じくらいの実力なんです。
たとえば、去年金メダルを取った小学校4年生の子は、先般の四谷大塚の全国統一小学校テストで14位でした。その結果を受けて、今夏にアイビーリーグ視察団としてハーバード、コロンビア、イエール、MIT、国連等の見学に招待されました。
最初は誰もが「算数オリンピックなんて、無縁の世界です」というところから始まっているんです。これは大事なポイントで、多くの親御さんが「うちの子には無理」と最初から決めつけてしまいがちですが、可能性を信じて取り組むことで、子どもは驚くほど成長するんです。
親子コミュニケーション術~第三者効果を活用した褒め方
——保護者の方とのコミュニケーションについて、具体的にどのような工夫をされていますか?
りんご塾では必ず授業後にフィードバックを行います。お子さんがどんなふうにがんばっていたか、どこで苦戦していたかなどを具体的にお伝えします。実はこのフィードバックが宝の山なのです。
たとえば「長い文章を読んで、そこから逃げずに問題が解けた」というフィードバックがあったとします。これを家で子どもに伝えるとき、「先生がそう言っていたよ。よくがんばったね。お母さん嬉しかったわ」というように伝えるんです。
これは「第三者効果」という心理学の知見を使っています。先生という第三者からの評価として伝えることで、子どもの意欲が格段に高まります。実はこれ、とても簡単なコピーアンドペーストのような作業なのに、ほとんどの親御さんがやっていない。でもこれだけで、子どもの学習意欲は大きく変わってきます。また「がんばった」という事実を褒めるのではなく、そのことを聞いて「嬉しかった」というメッセージで伝えることがポイントです。主語は「私(お母さん)」です。感情や想いの乗ったメッセージとなるため効果です。
——課題に対する親子のコミュニケーションについても、アドバイスをいただけますか?
「お子さんの課題はこの点です」と言われても、戸惑ってしまう親御さんが多いのではないでしょうか。多くの親御さんは指導者ではないわけですから。親御さんはコーチを目指せばよいとおもっています。課題について、お子さんに「どうすれば、次うまくできると思う?」って聞くだけでいいんです。
この質問にお子さまが回答をしてくれるなら、課題克服に向けた学びに期待が持てます。もしかするとお子さまからの回答がなく沈黙の時間だけ流れていくなんてこともあるかもしれません。でも、それでいいのです。
なぜかというと、人間の脳というのは、質問されると勝手に回答を作っちゃうんですよ。だからそれでいいんです。返答がなくてもお子さんは回答を自然に頭の中で積み立てているので、回答の有無に関係なく、適切な行動に向かうケースが多くあります。
子どもが自分で乗り越えることができない「課題」に直面した時には、塾に遠慮なく相談しましょう。課題を課題として終えてしまう習慣はよくありません。「同じような問題を、次に来たときにやってもらえますか」というふうに頼むと、課題が課題でなくなります。親のひと声により塾の対応にアクセントが生まれます。天才になる現実的な近道は、課題を1つ1つ潰していくプロセスにあるんだと思いますね。
——最後に、教育における保護者の役割について、あらためてアドバイスをいただけますか?
子どもを塾に預けるときに、単なる預ける場所として塾を活用してしまうととてももったいないんです。お父さんお母さんが共働きで忙しいから塾に預けておこうと、こういう無目的な塾の活用は勿体ないので、三者間で共通の課題を共有した方がいいと思います。
りんご塾であれば、身近な目標として算数検定や思考力検定に合格しよう! ということが共通の目標になります。期日に向かってがんばっていこうねというのが、大きなモチベーションになるわけです。生徒を中心に塾も親御さんも、〇月×日に向けて目標を持って行動する。共通の目標を持つと塾に通う意味付けが180度変わりますので、まずは目標を共有することを目標にしてみてください。
子どもは才能の塊なのです。導き方ひとつで天才になり得るのです。ただし、親の勝手な判断で可能性を低く見積もったり、逆に過度な期待でプレッシャーをかけたりするのは避けていただきたい。適度な加減で、楽しみながら学ぶことを基本に据えて、プロセスを大切にしていけば、必ず子どもは成長していきます。子育ては創造的な営みです。ぜひ保護者の方にも楽しんでいただきたいですね。
——本日はありがとうございました。
取材協力:りんご塾(運営:株式会社城南進学研究社)
※本記事に掲載している情報は記事執筆時点のものです。料金・キャンペーンなどの最新情報は各教室にお問い合わせください。