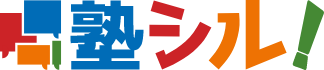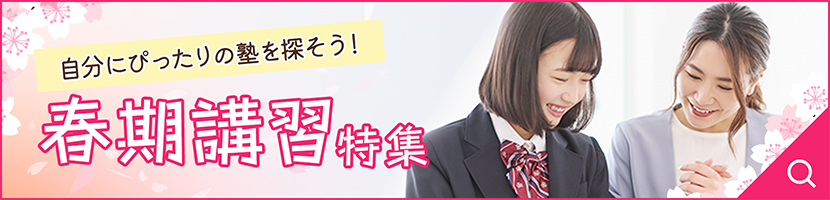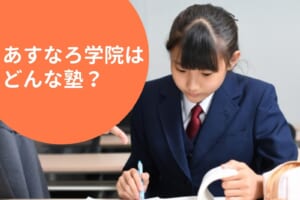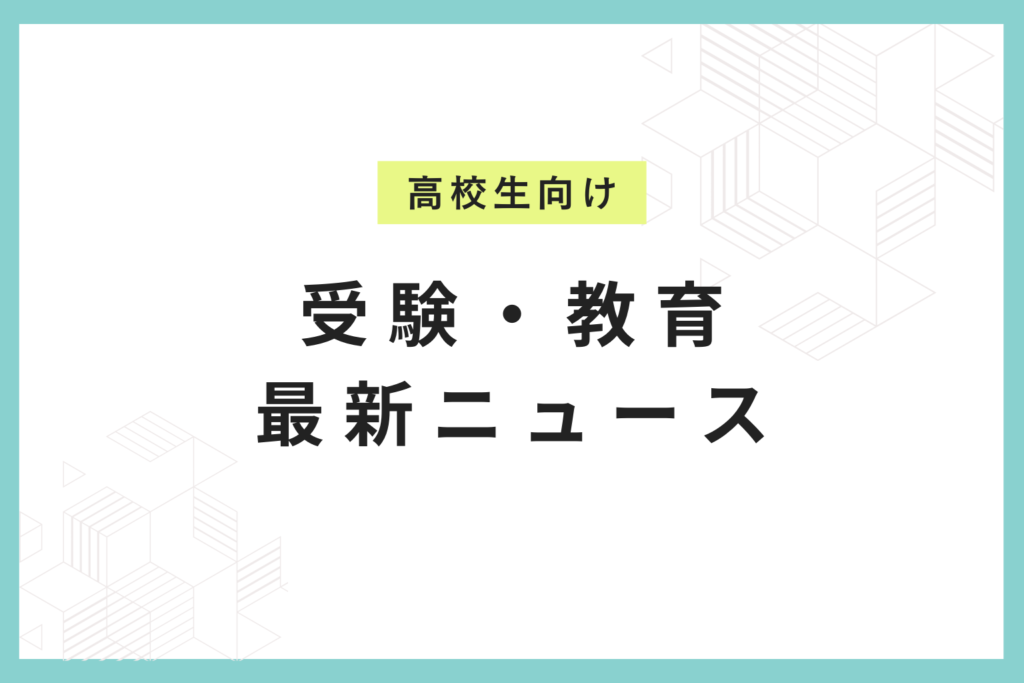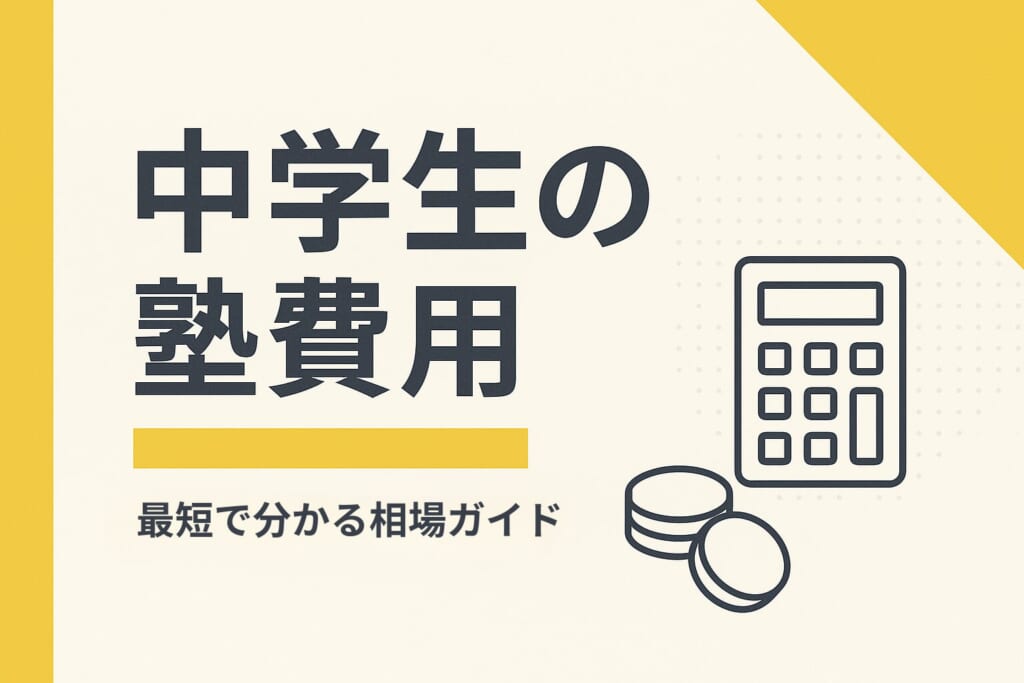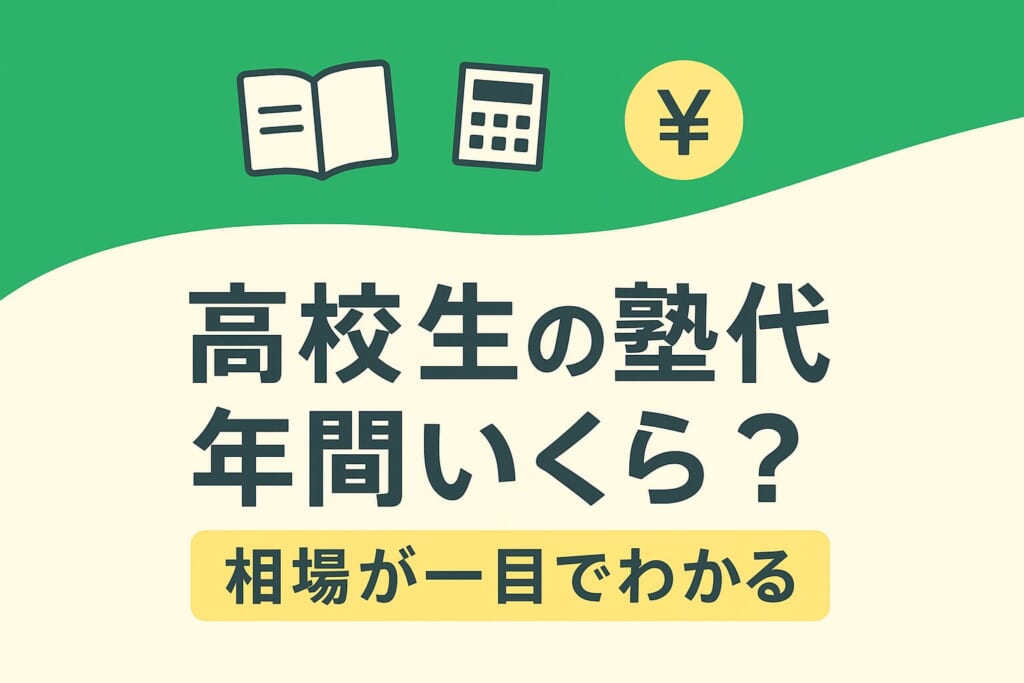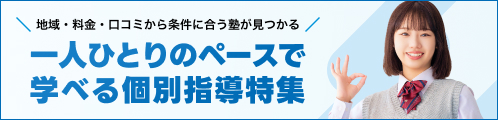- 不登校生が安心して学べる塾15選
- 出席扱い制度で内申点への影響を最小限に抑える方法
- 学年別の塾選びのコツと失敗しないチェックポイント
- 費用を抑える制度の活用方法
お子さんが不登校になると、多くの保護者が「学習の遅れ」や「将来の進路」について深い不安を感じます。しかし実際には、学校に行けなくても学習意欲を持ち続けているお子さんは少なくありません。
適切な塾を選ぶことで、お子さんは安心できる環境で学習を継続し、自信を取り戻しながら、復学や進学といった将来への道を切り開くことができます。また、文部科学省が定める条件を満たした塾での学習は「出席扱い」として認められ、内申点への影響を最小限に抑えることも可能です。
この記事では、不登校生の塾選びに必要な情報を体系的にまとめました。不登校生向けの塾の特徴から、目的別のおすすめ塾15選と選び方、出席扱い制度の活用方法、費用と支援制度まで、お子さんに最適な学習環境を見つけるためにぜひ参考にしてください。
- 不登校生が抱える学習への不安と塾通いの効果
- 不登校生の学習に関する実態調査から見える課題
- 「不登校でも塾には行く」という選択肢が増えている理由
- 塾通いがもたらす3つの心理的効果
- 不登校生向け塾の3つのタイプと特徴
- 個別指導塾|一人ひとりに寄り添う丁寧な指導
- オンライン塾|自宅で安心して学べる環境
- フリースクール|心の成長と学習の両立
- 不登校生におすすめの塾15選
- 心のケアを重視する塾 5校
- 学習の遅れ対策に強い塾 5校
- 受験対策に特化した塾 5校
- 不登校生の塾選びで失敗しないためのチェックポイント
- 不登校生の受け入れ実績と専門性
- 指導方針と教育理念
- 費用と返金保証制度
- 体験授業での相性確認
- 出席扱い制度への対応
- 通塾の利便性と安全性
- 保護者サポート体制
- 将来の進路選択肢への対応力
- 学年別・不登校生の塾の選び方
- 不登校の小学生の塾選び
- 不登校の中学生の塾選び
- 不登校の高校生の塾選び
- 出席扱い制度の活用方法と効果
- 文部科学省認定の出席扱い条件とは
- 昼間の通塾による生活リズム改善効果
- 出席扱い制度を使うための学校との連携方法
- 保護者が知っておきたい費用相場と賢い制度活用法
- 不登校生向け塾の費用相場と内訳
- 返金保証制度の活用方法
- 自治体の教育支援制度との併用
- よくある質問
- まとめ
不登校生が抱える学習への不安と塾通いの効果

不登校のお子さんを持つ保護者の多くが直面するのが「学習の遅れ」への不安です。しかし近年、「学校には行けないけれど塾には行ける」というお子さんも増加傾向にあり、多くの家庭で学習を続けられる選択肢が見えてきています。この章では、不登校生が抱える学習への不安の実態と、塾通いがもたらす可能性について詳しく解説します。
不登校生の学習に関する実態調査から見える課題
文部科学省の最新調査では、小中学校の不登校児童生徒数は約34万6千人に達し、過去最多を更新し続けています(文部科学省「不登校への対応について」)。多くの不登校生は、単に「学校に行きたくない」と思うだけでなく、複雑で深刻な学習への不安も抱えています。
不登校生が抱える学習面での具体的な不安を詳しく見ると、「勉強の遅れ」を最大の心配事として挙げるケースが多く、学年が上がるにつれて学習への不安が大きくなっています。特に高校受験を控えた不登校の中学生の保護者にとっては、切実な問題となっています。
さらに注目すべきは、不登校の理由として「無気力・不安」を挙げるお子さんが多いものの、それは必ずしも学習意欲の欠如を意味しないという点です。実際には「学びたい気持ち」を持ちながらも、学校という環境に適応できずにいるお子さんが少なくありません。この事実は、適切な学習環境さえ整えば、不登校の子どもたちも十分に学習が継続できることを示しています。
こうした背景から、保護者の多くが「子どもの学習継続」を支援する手段として、塾の利用を検討しています。
「不登校でも塾には行く」という選択肢が増えている理由
近年、教育現場で注目されているのが「学校には行けないが、塾には行く」という現象です。 この背景には、学校と塾の環境的な違いが大きく影響しています。
塾は学校と比べて圧倒的に「心理的な安全性」が高い環境です。学校では同級生との関係性や集団行動への適応が求められますが、個別指導塾では1対1の関係性が中心となり、お子さんが感じる社会的プレッシャーが軽減されます。
昼間の時間帯に通塾できることも重要なポイントです。 昼夜逆転の生活をしている不登校生にとって、昼間に塾通いをすることは、自然な生活リズムを回復するきっかけになります。実際に、昼間の通塾を続けた不登校生の多くが、生活リズムの改善を実感しています。
塾には「学習」という明確な目的があるため、お子さん自身も通いやすさを感じやすくなります。 学校のような複雑な人間関係や校則への適応を求められることなく、純粋に「学ぶ」ことに集中できる環境は、多くの不登校生にとって理想的な居場所です。
文部科学省も、適切な条件を満たす民間施設での学習を「出席扱い」として認める制度を設けています。この制度的な後押しも、塾という選択肢を選びやすくしている理由の一つです。
塾通いがもたらす3つの心理的効果
不登校生にとって塾通いは、単に学習の場を得るだけではなく、重要な心理的効果ももたらします。
- 自己肯定感の回復
不登校の子どもたちは、学校に行けない自分を責め、罪悪感を抱えることがあります。しかし、塾で「できる」「わかる」という成功体験を積み重ねることで、失われた自信を少しずつ取り戻すことができます。特に不登校の小学生の場合、基礎的な学習内容での成功体験が、その後の学習へのやる気に大きく影響します。
- 社会とのつながりの再構築
不登校により社会からの孤立を感じていた子どもたちが、塾という「第三の居場所」を得ることで、再び人とのつながりを感じられるようになります。講師との信頼関係を築くことは、その後の対人関係スキルの向上にも関係し、将来の復学や社会復帰への基盤ともなります。
- 将来への希望の回復
学習の遅れへの不安から「もう追いつけないかも」と感じていた子どもたちが、塾での個別指導により「まだ間に合う」という希望を見出すことができます。実際に、不登校の高校生の中には大学進学を実現している生徒も多く、適切なサポートがあれば十分に将来の目標達成が可能です。
これらの心理的効果は互いに関連し合い、好循環を生み出します。自信の回復が学習意欲を高め、社会とのつながりが将来への希望を育み、希望が更なる学習への動機となります。

不登校生の学習継続において最も重要なのは、お子さんの心理的安全性を確保することです。無理に学校復帰を急ぐのではなく、まずは塾という安心できる環境で学習への自信を取り戻すことから始めることをお勧めします。
不登校生向け塾の3つのタイプと特徴

不登校生向けの塾は、従来の一般的な学習塾とは異なる特徴を持っています。大きく分けて「個別指導塾」「オンライン塾」「フリースクール」の3つのタイプがあり、それぞれが異なるアプローチで学習支援を行っています。お子さんの心理状態や学習状況、将来の目標に応じて最適な塾のタイプを選ぶことがポイントとなります。
個別指導塾|一人ひとりに寄り添う丁寧な指導
個別指導塾は、不登校生にとって最も選択されることの多い塾のタイプです。1対1または1対2の少人数制指導により、お子さんのペースに合わせた学習が可能になります。
個別指導塾の主な特徴
不登校生の多くが抱える「人との関わりへの不安」を少しずつ解消しながら、学習意欲の回復を目指します。講師は単なる教科指導者ではなく、お子さんの心理状態を理解し、学習面と精神面の両方をサポートする存在となります。
不登校生向けの塾は昼間の時間帯での通塾が可能で、生活リズムの改善にも効果的です。個別指導塾の中には、午前10時から午後3時までの昼間の時間帯に専用コースを設けている塾もあり、同世代の生徒との接触を避けながら安心して通塾することができます。
お子さんの学力レベルや興味関心に応じた指導が受けられます。学校の授業に追いつくための復習から、将来の進路を見据えた発展的な学習まで、幅広いニーズに対応可能です。
個別指導の注意点
個別指導塾は費用が高額になりがちで、月額3万円から8万円程度の費用がかかることが一般的です。また、講師との相性が学習効果に大きく影響するため、体験授業で慎重に見極めることが重要になります。
オンライン塾|自宅で安心して学べる環境
オンライン塾は、外出への不安があるお子さんや、対面でのコミュニケーションに抵抗がある場合に最適です。自宅という安心できる環境で、質の高い教育を受けることができます。
オンライン塾の主な特徴
電車での移動や他の生徒との接触、塾の雰囲気への適応など、不登校生にとって負担となりがちな要素を避けながら学習を継続できます。
多くの不登校生向けのオンライン塾では、24時間いつでも質問できるシステムや、録画授業の繰り返し視聴機能を提供しています。昼夜逆転の生活リズムになっているお子さんでも、無理なく学習を始められます。
お子さんの興味や学力レベルに応じた多様な学習が可能です。AIを活用した個別最適化学習システムを導入している塾も多く、効率的な学力向上が期待できます。
オンライン塾の注意点
オンライン塾では対面での交流が限られるため、社会性の回復という面では効果が限定的です。また、自宅学習では自己管理能力が求められるため、保護者のサポートや学習習慣の定着に工夫が必要になります。インターネット環境やデバイスの準備など、技術的な要件を事前に確認することも重要です。
フリースクール|心の成長と学習の両立
フリースクールは、学習指導と心理的サポートを統合的に提供する教育機関です。従来の学校教育の枠組みにとらわれない、自由度の高い学習環境が特徴です。
フリースクールの主な特徴
お子さんが「ありのままの自分」を出すことができる環境づくりに力を入れています。カウンセラーや臨床心理士が在籍している施設も多く、学習面での不安だけでなく、不登校の根本的な原因にもアプローチできます。
座学だけでなく、アート活動、音楽、スポーツ、職業体験など、多様な活動を通じて学習意欲の回復を図ります。お子さんの自己肯定感の向上と新たな興味関心の発見につながります。
同じような経験を持つ仲間との出会いが可能です。お子さんは「自分だけではない」という安心感を得ながら、徐々に社会性を回復していきます。
お子さんの状態に応じて学習内容や進度を調整できます。文部科学省の出席扱い制度にも対応している施設が多く、制度的なサポートも受けられます。
フリースクールの注意点
学習進度は個人のペースに完全に依存するため、受験対策などの目標が明確な場合には、追加的な学習サポートが必要になることがあります。

塾選びで迷われた場合は、まず複数のタイプの塾で体験授業を受けることをお勧めします。お子さんの反応や表情の変化を注意深く観察することで、最適な学習環境が見えてきます。焦らず、お子さんのペースに合わせて選択してください。
不登校生におすすめの塾15選
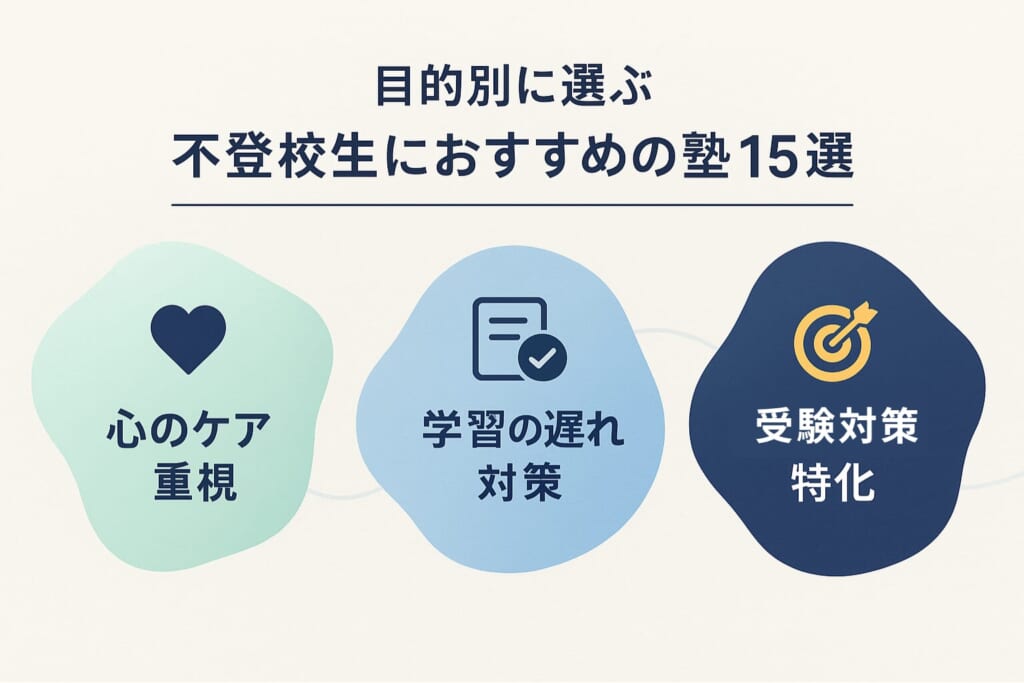
不登校生向けの塾選びにおいて最も重要なのは、お子さんの現在の状況と将来の目標に最適な学習環境を見つけることです。心のケアを重視する塾、学習の遅れ対策に強い塾、受験対策に特化した塾の3つのカテゴリーに分類し、それぞれの特徴と適性を詳しく解説します。
心のケアを重視する塾 5校
不登校の初期段階や、学習への不安が強いお子さんには、心理的サポートを重視する塾が最適です。これらの塾では、学習指導と並行してメンタルケアを行い、お子さんの自尊心回復と学習意欲の向上を図ります。
| 塾名 | 対象学年 | 入会金 | 月額料金 | 指導形式 | 対応エリア | 主な特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キズキ共育塾 | 小学生〜高校生・既卒生 | 16,500 円 | 28,000 円〜44,190 円 | 完全 1 対 1 個別指導(対面・オンライン) | 東京・神奈川・千葉・埼玉・愛知・大阪/全国(オンライン) | 不登校・発達障害専門、心のケア重視 |
| 学習支援塾ビーンズ | 小学生(高学年)〜高校生・既卒生 | 170,000 円 | 30,360 円〜40,920 円+授業外対応費 11,000 円〜27,500 円 | 個別指導・グループ授業・保護者相談・青春ラボ | 東京都新宿区飯田橋/オンライン | ビーンズメソッド、4 つのサポート |
| オンライン家庭教師ピース | 小学生・中学生・高校生 | 22,000 円 | 10,780 円〜24,915 円 | 完全オンライン・マンツーマン | 全国対応(一部海外も可) | 年齢の近い大学生講師、信頼関係重視 |
| ティントル | 小学生・中学生・高校生 | 要問い合わせ | 1,100 円〜3,300 円/30 分+ホームスクーリング 8,800 円 | オンライン個別指導・サポートチーム | 全国対応(オンライン) | 3 人体制サポート、出席扱い制度対応 |
| すらら | 小学 1 年生〜高校 3 年生 | 7,700 円〜11,000 円 | 8,800 円〜10,978 円 | AI オンライン教材・すららコーチ | 全国対応(オンライン・海外も可) | 無学年式 AI 教材、出席扱い実績 1,200 人以上 |
キズキ共育塾
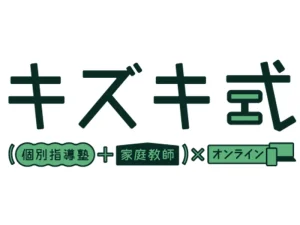
不登校・発達障害の生徒に特化した完全 1 対 1 個別指導塾。生徒一人ひとりの状況に合わせた学習計画と心のケアで、『もう一度勉強したい』という気持ちを全力でサポートします。
| 対象 | 小学生〜高校生・既卒生 |
| 対応エリア | 東京・神奈川・千葉・埼玉・愛知・大阪(教室)/全国(オンライン) |
| 指導形式 | 完全 1 対 1 個別指導(対面・オンライン) |
| 入会金 | 16,500 円 |
| 月額 | 28,000 円〜44,190 円 |
キズキ共育塾のおすすめポイント
- 完全 1 対 1 の個別指導で生徒のペースに合わせた学習が可能
- 不登校・発達障害の生徒の気持ちに寄り添う専門スタッフ
- 対面・オンライン選択可能で柔軟な学習環境
- 出席扱い制度への対応実績
この塾で力を伸ばしている生徒タイプ
キズキ共育塾の口コミ・評判
学習支援塾ビーンズ

参考:学習支援塾ビーンズ公式サイト(https://study-support-beans.com/)
悩める 10 代に特化し、ビーンズメソッドで心のケアから学習・進路までを総合的に支援。個別指導、グループ授業、保護者相談、居場所提供の 4 つのサポートで生徒の成長を見守ります。
| 対象 | 小学生(高学年)〜高校生・既卒生 |
| 対応エリア | 東京都新宿区飯田橋(教室)/オンライン |
| 指導形式 | 個別指導・グループ授業・保護者相談・青春ラボ(居場所) |
| 入会金 | 170,000 円 |
| 月額 | 30,360 円〜40,920 円(90 分 × 月 4 回)+授業外対応費 11,000 円〜27,500 円 |
学習支援塾ビーンズのおすすめポイント
- ビーンズメソッドによる心のケアと学習支援
- 4つのサポート(個別指導・グループ授業・保護者相談・青春ラボ)で総合的にサポート
- 悩める10代の心理的課題に深く向き合う専門性
- 保護者との密な連携体制
この塾で力を伸ばしている生徒タイプ
オンライン家庭教師ピース

参考:オンライン家庭教師ピース公式サイト(https://katekyo-peacenet.com/)
年齢の近い大学生講師が担当するオンライン家庭教師。不登校生の気持ちに寄り添い、信頼関係を築きながら学習をサポート。全国どこからでも受講可能で安心です。
| 対象 | 小学生・中学生・高校生 |
| 対応エリア | 全国対応(一部海外も可) |
| 指導形式 | 完全オンライン・マンツーマン家庭教師 |
| 入会金 | 22,000 円 |
| 月額 | 10,780 円〜24,915 円(60 分 × 月 4 回) |
オンライン家庭教師ピースのおすすめポイント
- 年齢の近い大学生講師が担当し親しみやすい
- 信頼関係を重視したコミュニケーション
- 全国どこでも受講可能なオンライン対応
- 比較的リーズナブルな料金設定
この塾で力を伸ばしている生徒タイプ
不登校専門オンライン個別指導ティントル

参考:不登校専門オンライン個別指導ティントル公式サイト(https://tintle.net/)
不登校・発達障害専門のオンライン個別指導。講師・サポートチーム・カウンセラーの 3 人体制で手厚くサポート。出席扱い制度対応で学校との連携も安心です。
| 対象 | 小学生・中学生・高校生 |
| 対応エリア | 全国対応(オンライン) |
| 指導形式 | オンライン個別指導・サポートチーム・ホームスクーリングコース |
| 入会金 | 要問い合わせ |
| 月額 | 1,100 円〜3,300 円/30 分(講師ランクにより変動)+ホームスクーリング 8,800 円 |
不登校専門オンライン個別指導ティントルのおすすめポイント
- 不登校・発達障害専門で 3 人体制(講師・サポートチーム・カウンセラー)の手厚いサポート
- 出席扱い制度対応で学校復帰をサポート
- 30 分単位の柔軟な受講とホームスクーリングコース
- カウンセラーによる心理サポート
この塾で力を伸ばしている生徒タイプ
すらら

参考:すらら公式サイト(https://surala.jp/)
無学年式 AI 教材で自分のペースで学べるオンライン学習。出席扱い認定実績 1,200 人以上。すららコーチのサポートで学習計画から保護者相談まで充実しています。
| 対象 | 小学 1 年生〜高校 3 年生 |
| 対応エリア | 全国対応(オンライン・海外も可) |
| 指導形式 | AI オンライン教材・すららコーチによる学習設計サポート |
| 入会金 | 7,700 円〜11,000 円 |
| 月額 | 8,800 円〜10,978 円(学び放題) |
すららのおすすめポイント
- 無学年式 AI 教材で学年を超えた学び直しが可能
- 出席扱い認定実績 1,200 人以上の豊富な実績
- すららコーチによる学習設計と保護者サポート
この塾で力を伸ばしている生徒タイプ
学習の遅れ対策に強い塾 5校
学習の遅れが進んでいる場合は、基礎学力の定着と効率的な学習方法の習得が必要です。これらの塾では、個別診断に基づいた学習計画で、確実に学力向上を図ります。
| 塾名 | 対象学年 | 入会金 | 月額料金 | 指導形式 | 対応エリア | 主な特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トライのオンライン個別指導塾 | 小学生・中学生・高校生 | 11,000 円 | 14,960 円〜 | 完全マンツーマン・オンライン | 全国対応(オンライン) | 33 万人から選抜されたプロ講師、W サポート |
| 東京個別指導学院 | 小学生・中学生・高校生 | 無料 | 要問い合わせ | 個別指導(1 対 1 または 1 対 2)・対面・オンライン | 全国 260 教室以上 | ベネッセグループ、入会金無料 |
| オンライン家庭教師 WAM | 小学生・中学生・高校生 | 要問い合わせ | 4,900 円〜 | オンライン個別指導(1 対 1) | 全国対応(オンライン) | 双方向型授業、返金保証制度 |
| クラスジャパン小中学園 | 小学生・中学生 | 11,000 円 | 27,500 円 | オンライン授業・担任制・個別学習 | 全国対応(オンライン) | 毎日のホームルーム、出席扱い制度対応 |
| まなぶてらす | 小学生・中学生・高校生 | 無料 | 13,200 円 | オンライン個別指導(1 対 1) | 全国対応(オンライン) | 多様な専門性、作文・自由研究対応 |
トライのオンライン個別指導塾
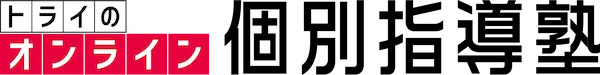
33 万人の教師から選抜されたプロ講師による完全マンツーマン指導。教育プランナーとの W サポートで学習の遅れを取り戻し、学校復帰や進路実現まで手厚くサポートします。
| 対象 | 小学生・中学生・高校生 |
| 対応エリア | 全国対応(オンライン) |
| 指導形式 | 完全マンツーマン・オンライン個別指導 |
| 入会金 | 11,000 円 |
| 月額 | 14,960 円〜(60 分 × 月 4 回) |
トライのオンライン個別指導塾のおすすめポイント
- 33 万人の教師から選抜された指導経験豊富な講師陣
- 教育プランナーによる W サポート体制で学習計画から進路相談まで対応
- 学校復帰に向けたアドバイスと学習の遅れを取り戻す具体的な計画策定
- 出席扱い制度への対応
この塾で力を伸ばしている生徒タイプ
東京個別指導学院

ベネッセグループ運営の個別指導塾。不登校生へのサポートに注力し、コーチングで自己肯定感を高めながら学習の遅れを取り戻します。進路指導も充実。
| 対象 | 小学生・中学生・高校生 |
| 対応エリア | 全国 260 教室以上 |
| 指導形式 | 個別指導(1 対 1 または 1 対 2)・対面・オンライン併用可 |
| 入会金 | 無料 |
| 月額 | 教室・学年により異なる(要問い合わせ) |
東京個別指導学院のおすすめポイント
- ベネッセグループの豊富な情報力を活かした進路指導
- コーチングスキルを持つ講師が心に寄り添い自己肯定感を高める
- お子さまのペースで効率よく学習の遅れを取り戻せる最適化された学習計画
この塾で力を伸ばしている生徒タイプ
東京個別指導学院の口コミ・評判
オンライン家庭教師WAM

双方向型の対話形式授業で自分で考える力を育成。地域の学校事情に精通し、基礎からの学び直しを丁寧にサポートします。
| 対象 | 小学生・中学生・高校生 |
| 対応エリア | 全国対応(オンライン) |
| 指導形式 | オンライン個別指導(1 対 1) |
| 入会金 | 要問い合わせ |
| 月額 | 4,900 円〜(40 分または 90 分・学年により異なる) |
オンライン家庭教師WAMのおすすめポイント
- 双方向型の対話形式授業で子ども自身が考え解決する力を引き出す
- 基本からのやり直しに対応した学習計画作成
- 返金保証制度あり
この塾で力を伸ばしている生徒タイプ
クラスジャパン小中学園
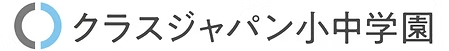
参考:クラスジャパン小中学園公式サイト(https://www.cjgakuen.com/)
出席扱い制度対応のオンラインフリースクール。毎日のホームルームと担任制で学習と生活を伴走支援。学校と連携し学習環境を整えます。
| 対象 | 小学生・中学生 |
| 対応エリア | 全国対応(オンライン) |
| 指導形式 | オンライン授業・担任制・個別学習 |
| 入会金 | 11,000 円 |
| 月額 | 27,500 円 |
クラスジャパン小中学園のおすすめポイント
- 毎日のホームルームと個別学習で規則正しい生活リズムをサポート
- 担任制による学習と生活面の伴走支援
- 学校と連携し出席扱いを目指せる実績
- オンラインで仲間とつながれる
この塾で力を伸ばしている生徒タイプ
まなぶてらす
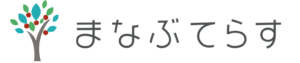
参考:まなぶてらす公式サイト(https://www.manatera.com/)
全国のプロ講師による完全 1 対 1 のオンライン個別指導。教科学習に加え、作文や自由研究のサポートも可能。生活リズムや進路の相談にも対応し、総合的に学びをサポートします。
| 対象 | 小学生・中学生・高校生 |
| 対応エリア | 全国対応(オンライン) |
| 指導形式 | オンライン個別指導(1 対 1) |
| 入会金 | 無料 |
| 月額 | 13,200 円(バリュープラン) |
まなびてらすのおすすめポイント
- 全国から集まった多様な専門性を持つプロ講師陣
- 教科学習だけでなく作文・読書感想文・自由研究にも対応
- 生活リズムや進路の相談も可能
- 柔軟なプラン設計で不定期受講も可能
この塾で力を伸ばしている生徒タイプ
受験対策に特化した塾 5校
高校受験や大学受験を控えている不登校生には、受験対策に特化した塾が効果的です。
| 塾名 | 対象学年 | 入会金 | 月額料金 | 指導形式 | 対応エリア | 主な特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 坪田塾 | 中学生・高校生・高卒生 | 要問い合わせ | 1 時間 1,640 円〜2,910 円(週 6 時間以上推奨) | 子別指導・オンライン対応 | 全国(校舎・オンライン校) | ビリギャルモデル、心理学的指導 |
| メガスタ | 小学生・中学生・高校生 | 19,800 円 | 小中学生 21,824 円〜・高校生 25,872 円〜 | オンライン個別指導(1 対 1) | 全国対応(オンライン) | 40,000 人の講師陣、25 年の実績、返金保証 |
| 河合塾 One | 中学生・高校生 | 無料 | 2,931 円〜(トレーナー付き+1,100 円) | AI おすすめ学習・オンライン映像授業 | 全国対応(オンライン) | 河合塾のノウハウ、AI 学習、低価格 |
| キズキ共育塾(受験対策) | 小学生〜社会人 | 16,500 円 | 28,000 円〜44,190 円 | 完全 1 対 1 個別指導・対面・オンライン | 東京・神奈川・千葉・埼玉・愛知・大阪/全国(オンライン) | 難関大学合格実績多数、心のケアも両立 |
| スタディサプリ高校講座・大学受験講座 | 高校生・大学受験生 | 無料 | 2,178 円(12 ヶ月一括払いで月 1,815 円) | オンライン映像授業・合格特訓コース | 全国対応(オンライン) | 40,000 本の授業見放題、圧倒的低価格 |
坪田塾

『ビリギャル』モデルの塾。心理学を用いて一人ひとりに合わせた「子」別指導で学習意欲を引き出し、反転学習と自習力育成で志望校合格を実現。正社員講師がチームで支えます。
| 対象 | 中学生・高校生・高卒生 |
| 対応エリア | 全国(校舎・オンライン校) |
| 指導形式 | 子別指導(個別指導)・オンライン対応 |
| 入会金 | 要問い合わせ |
| 月額 | 1 時間あたり 1,640 円〜2,910 円(週 6 時間以上推奨) |
坪田塾のおすすめポイント
- 『ビリギャル』モデルの実績
- 心理学を用いた 9 つの性格タイプ別指導
- 教科横断で正社員講師がチーム連携
- 『教えない、支える指導』で自習力を育成
- 反転学習で効率的に学力向上
この塾で力を伸ばしている生徒タイプ
坪田塾の口コミ・評判
メガスタ

参考:メガスタ公式サイト(https://www.online-mega.com/)
日本最大級のオンライン家庭教師。40,000 人の講師陣と 25 年の実績で不登校生の受験を徹底サポート。戻り学習で遅れを取り戻しながら志望校合格を実現します ※63。
| 対象 | 小学生・中学生・高校生 |
| 対応エリア | 全国対応(オンライン) |
| 指導形式 | オンライン個別指導(1 対 1) |
| 入会金 | 19,800 円 |
| 月額 | 小中学生 21,824 円〜・高校生 25,872 円〜 |
メガスタのおすすめポイント
- 全国 40,000 人の講師から最適な教師を選抜
- 25 年以上の不登校サポート実績
- 戻り学習で遅れを解消しながら受験・定期テスト対策
- 指導がない日も学習計画サポート
- スタッフと AI による授業品質チェック
この塾で力を伸ばしている生徒タイプ
河合塾One

参考:河合塾One公式サイト(https://www.kawaijukuone.co.jp/)
河合塾のノウハウを活かした AI 学習システム。月額 2,931 円から高校 5 教科の受験対策が可能。専任トレーナーのサポートで効率的に志望校合格を目指せます。
| 対象 | 中学生・高校生 |
| 対応エリア | 全国対応(オンライン) |
| 指導形式 | AI おすすめ学習・オンライン映像授業・専任トレーナーサポート(オプション) |
| 入会金 | 無料 |
| 月額 | 2,931 円〜(トレーナー付き+1,100 円/月) |
河合塾Oneのおすすめポイント
- 河合塾のノウハウを活かした AI おすすめ学習
- 高校5教科対応の豊富な映像授業コンテンツ
- 月額2,931円からの低価格で受験対策が可能
- 専任トレーナーによる学習計画・進路相談サポート(オプション)
この塾で力を伸ばしている生徒タイプ
キズキ共育塾(受験対策)
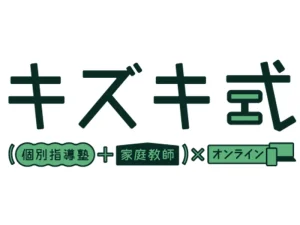
不登校・中退生専門の完全 1 対 1 個別指導塾。基礎から難関大学レベルまで対応し、東大・早慶上智など多数の合格実績。心のケアと学習指導を両立します。
| 対象 | 小学生〜社会人(高校受験・大学受験対応) |
| 対応エリア | 東京・神奈川・千葉・埼玉・愛知・大阪・オンライン全国対応 |
| 指導形式 | 完全 1 対 1 個別指導・対面・オンライン併用可 |
| 入会金 | 16,500 円 |
| 月額 | 28,000 円〜44,190 円 |
キズキ共育塾のおすすめポイント
- 東大・早慶上智など難関大学合格実績多数
- 基礎から難関大学レベルまで対応
- 不登校・中退・ひきこもり・再受験の専門的サポート
- 完全 1 対 1 のオーダーメイド受験指導
- 心理面のケアと学習指導の両立
この塾で力を伸ばしている生徒タイプ
キズキ共育塾の口コミ・評判
スタディサプリ高校講座・大学受験講座

参考:スタディサプリ高校講座・大学受験講座公式サイト(https://studysapuri.jp/course/high/1/)
リクルート提供のオンライン映像授業。40,000 本の有名講師授業が月額 2,178 円で見放題。合格特訓コースで担当コーチの個別指導も受けられます。
| 対象 | 高校生・大学受験生 |
| 対応エリア | 全国対応(オンライン) |
| 指導形式 | オンライン映像授業・合格特訓コース(担当コーチ付き) |
| 入会金 | 無料 |
| 月額 | 2,178 円(ベーシックコース・12 ヶ月一括払いで月 1,815 円) |
スタディサプリ高校講座・大学受験講座のおすすめポイント
- 大手予備校の有名講師による 40,000 本以上の授業が見放題
- 月額 2,178 円という圧倒的な低価格
- 共通テスト対策・志望校対策・小論文対策講座が充実
- 合格特訓コースで担当コーチの個別指導と質問対応が可能
この塾で力を伸ばしている生徒タイプ

塾選びで最も重要なのは「相性」です。どんなに評判の良い塾でも、お子さんとの相性が合わなければ効果は期待できません。必ず体験授業を受け、お子さん自身の感想を最優先に判断してください。また、複数の塾を比較検討し、焦らずに時間をかけて選ぶことをお勧めします。
不登校生の塾選びで失敗しないためのチェックポイント

不登校生向けの塾選びは、一般的な塾選びとは異なる独自の視点が必要です。お子さんの心理状態や学習状況を考慮し、長期的な成長を見据えた慎重な判断が求められます。この章では、塾選びで後悔しないための重要なチェックポイントを詳しく解説します。
不登校生の受け入れ実績と専門性
一般的な学習塾と不登校専門塾では、指導アプローチが根本的に異なるため、不登校生への指導経験を十分に持っているかどうかの確認が重要となります。
確認ポイント
特に重要なのは、「不登校生も受け入れています」という表面的な対応ではなく、不登校生特有の学習課題や心理的な配慮について、具体的な対策を行っているかどうかです。実績のある塾では、不登校生の段階的な学習復帰プログラムや、保護者向けの相談体制が整備されています。
指導方針と教育理念
不登校生にとって、塾の教育理念や指導方針は学習効果に直結する重要な要素です。お子さんの価値観や学習スタイルに合った塾を選ぶことが重要です。
確認ポイント
例えば、学習への不安が強いお子さんには、競争よりも個人の成長を重視する塾が適しています。一方、学習意欲が回復してきたお子さんには、適度な目標設定と達成感を提供する塾が効果的です。
費用と返金保証制度
不登校生向けの塾は一般的な塾よりも費用が高額になる傾向があります。月額 1 万円から 8 万円超まで幅広い価格帯があるため、費用対効果を慎重に検討する必要があります。
確認ポイント
特に注目すべきは返金保証制度です。多くの不登校専門塾では、入会後一定期間内に効果が見られない場合の返金保証を設けています。ただし、返金条件は塾によって大きく異なるため、契約前に確認が必要です。
体験授業での相性確認
不登校生にとって講師との相性は、学習効果を左右する最も重要な要素の一つです。体験授業は単なる授業内容の確認ではなく、お子さんと講師の人間関係を見極める貴重な機会です。
確認ポイント
体験授業後は、お子さんの率直な感想を聞くことが重要です。「また行きたい」「先生が優しかった」といった前向きな反応が見られれば、相性の良い証拠です。
出席扱い制度への対応
文部科学省認定の出席扱い制度を活用できるかどうかは、内申点への影響を考える上で極めて重要です。制度に対応している塾でも、実際の認定取得には学校との綿密な連携が必要です。
確認ポイント
出席扱い制度は塾が対応していても、最終的な認定は学校の判断に委ねられます。そのため、学校との良好な関係構築をサポートしてくれる塾を選ぶことが重要です ※25。
通塾の利便性と安全性
不登校生にとって通塾のハードルを下げることは、継続的な学習のために不可欠です。立地や通塾時間、安全性について十分な検討が必要です。
確認ポイント
お子さんによっては、同級生との遭遇を避けたいという心理的な配慮が重要です。昼間の時間帯に通塾できる塾を選ぶことで、生活リズムの改善効果も期待できます。
保護者サポート体制
不登校生の塾選びでは、お子さんへの指導だけでなく、保護者への支援体制も重要な判断材料となります。
確認ポイント
保護者の心理的な負担の軽減は、お子さんの学習環境改善に直結します。保護者が安心して塾に任せられる体制が整っているかを確認しましょう。
将来の進路選択肢への対応力
不登校生の進路は多様化しており、従来の高校受験・大学受験だけでなく、通信制高校や専門学校、就職など様々な選択肢があります。塾がこれらの多様な進路に対応できるかを確認することが重要です。
確認ポイント
将来の選択肢を狭めることなく、お子さんの可能性を最大限に引き出してくれる塾を選ぶことで、長期的な成長と自立を支援できます。

塾選びは一度で完璧にする必要はありません。お子さんの成長に合わせて塾を変更することも選択肢の一つです。まずは体験授業を通じて、お子さんが安心して学べる環境かどうかを最優先に判断してください。
学年別・不登校生の塾の選び方

不登校生の塾選びは、学年によってアプローチが異なります。小学生では基礎学力の定着と学習習慣の再構築、中学生では高校受験を見据えた内申点対策と学力向上、高校生では大学進学や就職に向けた将来設計が中心となります。
この章では、学年別の具体的な塾の選び方と、それぞれの段階で重視すべきポイントについて詳しく解説します。
不登校の小学生の塾選び
小学生の不登校の場合は、学習の遅れよりも「学ぶことへの興味」を取り戻すことが最優先となります。文部科学省の調査では、不登校理由として「無気力・不安」が 51.8%と最も多く ※2、学習に対して良くないイメージを抱えているケースが少なくありません。
【出典】
※2 文部科学省「不登校への対応について」
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/futoukou/main.htm
小学生向け塾選びのポイント
- 遊び要素を取り入れた学習アプローチ
不登校の小学生には、従来の「勉強」という概念から離れ、ゲーム性や体験型学習を重視する塾が効果的です。算数であれば具体的な教材を使った操作、国語では読み聞かせや創作活動など、「楽しい」と感じられる学習体験を提供してくれる塾を選ぶことが重要です。
- 短時間集中型の学習プログラム
不登校の小学生は集中力が続かない場合が多いため、30 分から 1 時間程度の短時間集中型プログラムを採用している塾が適しています。長時間の学習を初めから行うよりも、お子さんの体調や気分に合わせて柔軟に時間調整できる塾を選びましょう。
- 保護者との密な連携体制
小学生の場合、家庭での学習サポートが重要になります。定期的な面談や学習状況の共有、家庭学習のアドバイスなど、保護者と塾が一体となってお子さんを支える体制が整っている塾を選ぶことが必要です。
不登校の小学生におすすめの塾タイプ
小学生の不登校では、個別指導塾が最も適しています。特に不登校専門コースを設けている塾では、小学生の心理状態を理解した指導が期待でき、遊び要素を取り入れた学習アプローチや短時間集中型プログラムなど、お子さんの発達段階に合わせた配慮がなされています。また、昼間の時間帯に通塾することで、規則正しい生活リズムを築いていくことも可能です。
オンライン塾も選択肢の一つですが、小学生の場合は対面でコミュニケーションを取る方が学習効果が高い傾向にあるため、まずは個別指導塾での体験授業を受けることをおすすめします。
おすすめの塾
不登校の中学生の塾選び
中学生の不登校の場合は、高校受験という明確な目標があるため、より戦略的な塾選びが必要になります。内申点への影響を最小限に抑えながら、受験に必要な学力を確実に身につける必要があります。
中学生向け塾選びのポイント
- 出席扱い制度の積極的活用
文部科学省の出席扱い制度を活用できる塾を選ぶことで、内申点への影響を軽減できます。この制度を利用するためには、学校との連携が不可欠であり、制度申請のサポートを行っている塾を選ぶことが重要です。
- 教科バランス型の学習プログラム
高校受験では 5 教科すべてが重要になるため、特定科目に偏らない総合的な学習プログラムを提供する塾が適しています。特に、学校で履修できていない単元の補完と、受験に向けた応用力の養成を両立できる塾を選びましょう。
- 進路相談とメンタルサポートの充実
中学生の不登校では、将来への不安が学習意欲に大きく影響します。進路相談や心理的サポートを専門とするカウンセラーが在籍している塾や、不登校経験者による体験談を聞ける環境がある塾が効果的です。
- 模試や検定試験への対応
客観的な学力把握のため、模擬試験の受験機会を提供している塾を選ぶことが重要です。また、英語検定や漢字検定などの資格取得サポートがある塾では、自信回復にもつながります。
不登校の中学生におすすめの塾タイプ
中学生の不登校では、高校受験という明確な目標があるため、出席扱い制度を活用できる個別指導塾が最も適しています。特に5教科をバランスよく学べるプログラムを持つ塾を選ぶことで、学校で履修できていない単元の補完と受験に向けた応用力の養成を両立できます。また、進路相談やメンタルサポートが充実している塾では、将来への不安を軽減しながら学習意欲を高めることができます。
客観的な学力把握のため、模擬試験の受験機会を提供している塾や、英語検定・漢字検定などの資格取得サポートがある塾も効果的です。なお、同級生との接触を避けたい場合は、通塾時間帯や教室の配慮について事前に確認することが必要です。
おすすめの塾
不登校の高校生の塾選び
高校生の場合の不登校では、大学受験や就職など、より具体的な将来設計が課題となります。学習面だけでなく、社会人としての基礎的なスキル習得も視野に入れた塾選びが重要です。
高校生向け塾選びのポイント
- 大学受験対策の専門性
不登校の高校生には、一般入試だけでなく、総合型選抜(旧 AO 入試)や学校推薦型選抜への対応も重要です。小論文指導や面接対策、志望理由書の作成支援など、多様な入試形態に対応できる塾を選ぶことが必要です。
- 社会人基礎力の養成
コミュニケーション能力、問題解決能力、チームワークなど、社会人として必要な基礎的スキルの養成プログラムがある塾は、就職を考えている高校生にとって特に有効です。
- キャリア教育と進路指導
将来の職業選択や進路決定に関する専門的な指導を受けられる塾を選ぶことで、お子さんの将来への不安を軽減できます。インターンシップの紹介や職業体験の機会を提供している塾もあります。
- 軟な学習スケジュール
高校生の場合、アルバイトや他の活動との両立を考える必要があります。夜間や土日の授業、オンライン授業との併用など、柔軟なスケジュール調整が可能な塾を選ぶことが重要です。
不登校の高校生におすすめの塾タイプ
高校生の場合は、大学受験や就職など具体的な将来設計が課題となるため、受験対策に特化した個別指導塾やオンライン塾が効果的です。一般入試だけでなく、総合型選抜(旧AO入試)や学校推薦型選抜への対応も重要で、小論文指導や面接対策、志望理由書の作成支援など多様な入試形態に対応できる塾を選ぶ必要があります。
また、就職を考えている高校生には、コミュニケーション能力や問題解決能力などの社会人基礎力を養成するプログラムがある塾も有用です。なお、同世代との学力格差への不安や将来への焦りが強い場合は、同じ境遇の仲間との交流機会を提供している塾や、不登校経験者による体験を聞ける環境がある塾も効果的です。
おすすめの塾

学年別の塾選びでは、お子さんの発達段階と将来の目標を明確にすることが最も重要です。特に中学生では出席扱い制度の活用、高校生では多様な進路選択肢の検討を意識しましょう。まずは体験授業を通じて、お子さんとの相性を確認することから始めることをお勧めします。
出席扱い制度の活用方法と効果

不登校生にとって「出席扱い制度」は、学習継続と将来の進路選択を両立させる重要な制度です。文部科学省が定めた条件を満たす塾での学習は、正式に学校出席として認定され、内申点への影響を最小限に抑えることができます。
しかし、この制度を効果的に活用するためには、適切な塾選びと学校との連携が不可欠です。この章では、出席扱い制度の具体的な条件から、昼間の通塾による生活リズム改善効果、学校との連携方法まで、制度を最大限に活用するための実践的な方法を詳しく解説します。
文部科学省認定の出席扱い条件とは
出席扱い制度を活用するためには、文部科学省が定めた7つの条件をすべて満たす必要があります ※3。これらの条件は、単に塾に通うだけでは満たされず、学校との連携や適切な学習計画が求められます。
出席扱い認定の7つの必須条件
- 保護者と学校との十分な連携・協力関係
定期的な面談や学習状況の報告が必要です。月1回以上の学校との連絡を推奨している自治体が多く見られます。
- ICT や郵送等を活用した学習活動
オンライン学習システムや通信教材を活用した学習記録の提出が求められます。学習ログの保存と定期的な提出が重要なポイントです。
- 訪問等による対面指導の適切な組み合わせ
オンラインのみではなく、定期的な対面指導や面談が必要です。月2回以上の対面指導を条件とする学校が一般的です。
- 学習の理解の程度を踏まえた計画的な学習プログラム
お子さんの学力レベルに応じた個別カリキュラムの作成と実施が必要です。
- 校長が対面指導や学習活動の状況等を十分に把握
学校側が学習状況を定期的に確認し、適切な評価を行える体制が必要です。
- 学校外の公的機関や民間施設等で相談・指導を受けられない場合
ICT 等を活用した学習活動を出席扱いとするのは、他の支援機関を利用していない場合に限定されます。
- 学習活動の成果を学校の教育課程に照らして評価
塾での学習内容が学校のカリキュラムと整合性を持つ必要があります。
【出典】
※3 文部科学省「義務教育段階の不登校児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けている場合の指導要録上の出欠の取扱いについて」
https://www.mext.go.jp/content/1422155\_001.pdf
出席扱い制度に対応した塾の選び方
出席扱い制度に対応できる塾は、学習管理システムが充実しており、お子さんの学習進度や理解度を詳細に記録・報告できる体制が整っているという特徴があります。また、学校との連携経験が豊富で、出席扱い申請に必要な書類作成や報告書の提出をサポートできる塾を選ぶことが重要です。さらに、文部科学省の学習指導要領に準拠したカリキュラムを提供し、学校の授業内容との整合性を保てる塾が理想的です。
おすすめの塾
昼間の通塾による生活リズム改善効果
不登校生の多くが抱える「昼夜逆転」の問題は、学習面だけでなく心身の健康にも影響を与えます。昼間の塾通いは、生活リズムの改善に大きな効果をもたらします。
昼間の通塾がもたらす3つの効果
- 生体リズムの正常化
午前中から午後にかけての塾通いにより、夜間の自然な睡眠サイクルを取り戻すことができます。特に午前10時から午後3時の時間帯での学習は、体内時計のリセットに効果的です。
- 社会性の維持・向上
昼間の活動により、一般的な社会生活のリズムに慣れることができます。これは将来の復学や就職に向けた準備となります。
- 学習効率の向上
午前中の集中力が高い時間帯を活用することで、学習効果を高めることができます。研究によると、午前10時から正午にかけては記憶力と集中力が最も高まる時間帯とされています。
昼間の通塾を支援する塾の取り組み
多くの不登校専門塾では、昼間の通塾を支援するプログラムを提供しています。例えば、午前中から開校している個別指導塾では、お子さんの生活リズムに合わせて段階的に通塾時間を早める「生活リズム改善プログラム」などを実施しているケースもあります。
また、昼間の時間帯に特化したオンライン授業を提供する塾もあり、自宅での学習から始めて徐々に外出への抵抗感を減らしていくアプローチを取っています。これらの取り組みは、出席扱い制度の「計画的な学習プログラム」の条件を満たすだけでなく、お子さんの総合的な回復を支援する効果があります。
出席扱い制度を使うための学校との連携方法
出席扱い制度を活用するためには塾と並行して学校との連携も重要となります。
効果的な学校連携の5つのステップ
- 初期相談での制度説明
まず、担任教師やスクールカウンセラーに出席扱い制度活用の意向を伝え、学校側の理解と協力を得ることが重要です。
- 塾選択時の学校への相談
塾を選ぶ前に、学校側に相談し、どのような塾であれば出席扱いの対象となるかを確認します。学校によって判断基準が異なる場合があるため、事前の確認が必要です。
- 学習計画の共同作成
塾と学校が連携して、お子さんの学力レベルと目標に応じた学習計画を作成します。この計画は、学校の教育課程との整合性を保つ必要があります。
- 定期的な進捗報告
月1回以上の頻度で、塾での学習状況を学校に報告します。学習時間、理解度、課題の取り組み状況などを詳細に記録し、学校側が適切に評価できるように情報を提供します。
- 復学準備のサポート
出席扱い制度を活用しながら、段階的な復学に向けた準備を進めます。学校行事への部分参加や定期テストの受験など、無理のない範囲で学校との接点を増やしていきます。
学校との連携をスムーズに行うコツ
学校との連携は保護者が積極的に関わることが不可欠です。定期的な面談では、お子さんの学習状況だけでなく、心理的な変化や将来への意欲についても共有することが重要です。
また、塾側が学校との連携経験を豊富に持っているかも重要となります。出席扱い制度に対応した実績のある塾では、学校への報告書作成や連携方法について具体的なアドバイスを受けることができます。

出席扱い制度の活用は、単なる出席日数の確保以上の意味を持ちます。制度を通じて学校との信頼関係を築き、お子さんの学習意欲を高めることで、復学や進学への道が開けてきます。まずは学校への相談から始めて、お子さんのペースに合わせた制度活用を検討してください。
保護者が知っておきたい費用相場と賢い制度活用法

不登校生向けの塾選びにおいて、多くの保護者が直面するのが費用面での不安です。一般的な学習塾と比較して、不登校専門塾は個別対応やメンタルサポートが充実している分、費用が高額になる傾向があります。しかし、返金保証制度や自治体の教育支援制度を適切に活用することで、費用負担を大幅に軽減することが可能です。この章では、不登校生向け塾の具体的な費用相場から、賢い制度活用法まで、保護者が知っておきたい費用面の全体像を詳しく解説します。
不登校生向け塾の費用相場と内訳
不登校生向け塾の費用は、指導形式やサポート内容によって大きく異なります。一般的な学習塾と比較して1.5倍から3倍程度の費用がかかることもあり、これは専門的な指導とメンタルサポートの対価として理解する必要があります。
個別指導塾の費用相場
個別指導塾では、講師1人に対して生徒1人または2人の少人数制指導が基本となるため、講師の人件費が高くなります。特に不登校専門の研修を受けた講師による指導では、月額50,000円以上が一般的となっています。
オンライン塾の費用相場
オンライン形式は教室運営費がかからない分、対面指導より安価に設定されることが多く、費用を抑えたい家庭には魅力的な選択肢となります。
フリースクールの費用相場
フリースクールは、学習指導に加えて心理カウンセリングや社会体験活動も含まれるため、高額な費用設定となる傾向があります。
返金保証制度の活用方法
不登校生向け塾の多くが導入している返金保証制度は、万が一の際の費用負担を軽減する重要な仕組みです。お子さんとの相性や指導効果に不安がある場合、この制度を積極的に活用することで安心して塾選びを進めることができます。
主要な返金保証制度の種類
入会から1〜2ヶ月以内であれば、理由を問わず入会金や授業料の全額または一部が返金される制度です。多くの塾で採用されており、お子さんとの相性を確認する期間として活用できます。
一定期間内に成績向上が見られない場合、追加授業を無料で提供したり、授業料の一部を返金する制度です。ただし、不登校生の場合は従来の成績評価が困難なため、学習意欲の向上や出席日数の改善など、より柔軟な評価基準が設定されることが多くなっています。
講師との相性が合わない場合、無料で講師変更を行い、それでも改善されない場合は返金に応じる制度です。不登校生にとって講師との相性は特に重要なため、この制度の有無は塾選びをする際の重要な判断材料となります。
返金保証制度を活用する際の注意点
返金保証制度は、塾選びのリスクを軽減する有効な仕組みですが、適切に活用するためにはいくつかの注意点があります。
・保証期間や条件を事前に詳しく確認する
・返金申請に必要な書類や手続きを把握しておく
・保証対象外となる条件(欠席回数など)を理解する
自治体の教育支援制度との併用
多くの自治体では、不登校生への教育支援制度を設けており、塾費用の一部補助や無料の学習支援サービスを提供しています。これらの制度を活用することで、費用負担を大幅に軽減することが可能です。
主要な自治体支援制度
全国の自治体が運営する適応指導教室では、無料で学習指導やカウンセリングを受けることができます。塾と併用することで、基礎的な学習は適応指導教室で、専門的な受験対策は塾で行うという効率的な学習計画が立てられます。
一部の自治体では、就学援助制度の対象を塾費用まで拡大しており、月額10,000 円〜30,000円程度の補助を受けることができます。所得制限はありますが、該当する家庭では大きな支援となります。
こども家庭庁のモデル事業として「地域における不登校のこどもへの切れ目ない支援事業」が 2025年度から全国20自治体で実施されています(※2)。不登校支援コーディネーターの配置や相談支援に加えて、一部の自治体ではフリースクール利用費の補助(月額2〜4万円程度)や交通費支援など、家庭の費用負担を軽減する制度も設けられています。
【出典】
※2 こども家庭庁「地域における不登校のこどもへの切れ目ない支援事業」https://www.cfa.go.jp/procurement/koubo-futoukou
自治体支援制度を活用する手順
これらの自治体支援制度を効果的に活用するためには、以下の手順で進めることをお勧めします。
- 居住自治体の教育委員会に不登校支援制度を問い合わせる
- 適応指導教室の見学と利用条件の確認
- 就学援助制度の申請要件と手続き方法の確認
- 塾選びと並行して制度利用の準備を進める
自治体制度と民間塾の効果的な併用方法
自治体制度と民間塾を併用する場合、それぞれの特徴を活かした学習計画を立てることが重要です。適応指導教室では社会性の回復と基礎学習を、民間塾では個別性の高い専門指導をという役割分担をすることで、限られた予算で最大の効果を得ることができます。
費用面での制約があっても、適切な制度活用により質の高い教育支援を受けることは十分可能です。まずは居住地域の支援制度を調べ、塾選びと並行して活用できる制度を見つけることから始めましょう。

不登校支援における費用負担は多くの家庭で深刻な問題となっていますが、返金保証制度や自治体支援を組み合わせることで、負担を最小限に抑えながら最適な学習環境を確保することができます。特に初回返金保証制度は、お子さんとの相性を確認する貴重な機会として積極的に活用することをお勧めします。
よくある質問

不登校でも高校受験・大学進学はできますか?
はい、可能です。不登校であっても、適切な学習環境で継続的に学習を進めることで、高校受験や大学進学を実現している生徒は多くいます。
特に重要なのは、出席扱い制度の活用です。文部科学省が定める条件を満たした塾での学習は「出席扱い」として認められ、内申点への影響を最小限に抑えることができます。
不登校生向けの塾の多くは受験対策にも対応しており、一人ひとりの学力レベルに応じた個別カリキュラムで、基礎からしっかり学び直すことができます。将来の選択肢を広げるためにも、早めに適切な学習環境を整えることをおすすめします。
学校に行っていないと勉強の遅れは取り戻せませんか?
取り戻せます。不登校生向けの塾では、お子さんの現在の学力レベルに合わせて、必要に応じて学年をさかのぼって基礎から学び直すことができます。
個別指導塾やオンライン塾では、一人ひとりの理解度に応じたペースで学習を進められるため、集団授業で感じていた「ついていけない」というプレッシャーを感じることなく、着実に学力を積み上げられます。
実際に、多くの不登校生が塾での学習を通じて学習の遅れを取り戻し、同学年の学習内容に追いつき、さらには志望校合格を実現しています。重要なのは「今から始める」ことです。焦らず、お子さんのペースで継続することで、確実に学力は向上します。
出席扱い制度を利用するにはどうすればいいですか?
出席扱い制度を利用するには、以下の手順が必要です。
1. 条件を満たす塾を選ぶ
文部科学省が定める 7 つの条件(ICT を活用した学習、対面指導との組み合わせ、学校との連携など)を満たす塾を選択します。
2. 学校への相談
保護者が在籍校の担任や校長に相談し、出席扱いの申請意思を伝えます。この際、塾側が提供する学習計画書や指導内容の資料を提出します。
3. 学校長の承認
最終的な判断は学校長が行います。承認されれば、塾での学習が出席として認定されます。
4. 定期的な報告
塾側から学校へ定期的に学習状況の報告を行い、継続的な連携を維持します。
出席扱い制度に対応している塾では、この手続きをサポートしてくれるため、まずは体験授業の際に相談してみることをおすすめします。
塾の費用はどのくらいかかりますか?利用できる支援制度はありますか?
不登校生向けの塾の費用は、塾のタイプや指導形式によって大きく異なります。
費用の目安:
個別指導塾:月額 30,000 円〜80,000 円
オンライン塾:月額 10,000 円〜40,000 円
フリースクール:月額 30,000 円〜50,000 円以上
これに加えて、入会金(10,000 円〜50,000 円)、教材費、設備費などがかかります。
利用できる支援制度:
自治体の教育支援金制度(地域によって異なる)
就学援助制度(一部の塾で利用可能)
特定扶養控除などの税制優遇措置
塾独自の奨学金制度や減免制度
また、多くの塾で返金保証制度を設けているため、お子さんとの相性を確認してから本格的に始めることができます。費用面で不安がある場合は、まずは居住地域の自治体窓口に相談し、利用できる支援制度を確認することをおすすめします。
体験授業で子どもとの相性を確認できますか?途中で辞めることはできますか?
はい、ほとんどの塾で無料体験授業を実施しており、お子さんと講師の相性や教室の雰囲気を事前に確認できます。
不登校生にとって、講師との相性は学習効果に直結する最も重要な要素です。体験授業では以下の点を確認しましょう。
確認ポイント
・お子さんが安心して話せる雰囲気か
・講師がお子さんのペースを尊重しているか
・不登校への理解と指導経験があるか
・教室やオンライン環境が快適か
途中での退会について
多くの塾では月単位での契約となっており、途中退会も可能です。また、以下の制度を設けている塾もあります:
・初回返金保証(入会から 1〜2 ヶ月以内の返金)
・講師変更制度(相性が合わない場合)
・休会制度(一時的に休むことができる)
無理に続ける必要はありません。お子さんの様子を見ながら、最適な環境を探すことが大切です。
まとめ
不登校のお子さんにとって、適切な塾選びは学習継続と将来への希望をつなぐ重要な選択です。この記事でご紹介した3つの塾タイプ(個別指導塾、オンライン塾、フリースクール)から、お子さんの状況と性格に最も適したものを選びましょう。
特に重要なのは、出席扱い制度の活用、学年に応じた戦略的な塾選び、そして保護者の皆さんが抱える費用面での不安への対処法です。小学生には基礎学力の再構築、中学生には高校受験対策、高校生には大学進学準備と、それぞれの段階で求められる支援は異なります。また、昼間の通塾による生活リズムの改善も大きな効果をもたらします。複数の選択肢を検討することで、最適な学習環境が見つかります。
不登校は決して恥ずかしいことではありません。お子さんの個性と可能性を信じ、最適な学習環境を見つけることで、必ず新しい道が開けます。まずは気になる塾への問い合わせから始めてみてください。

監修者
キズキ共育塾・不登校相談員
伊藤 真依
高校不登校を経て、法学部に進学、2022年に卒業。同年、株式会社キズキ(キズキ共育塾)に就職。
2024年8月まで名古屋校にて教室長を務め、多くの不登校のご家庭との相談を実施。
現在は不登校相談に加え、イベント登壇や自社メディア「不登校オンライン」の運営などに携わり、不登校に関する課題をより広く社会に提起するための活動に尽力している。
◆不登校・中退・通信制高校からの受験塾 キズキ共育塾
https://kizuki.or.jp/
※本記事に掲載している情報は記事執筆時点のものです。料金・キャンペーンなどの最新情報は各教室にお問い合わせください。