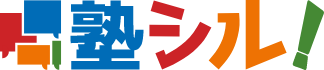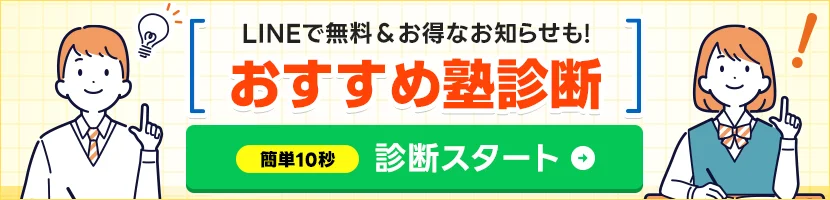「放置しない」をコンセプトにオンライン指導で生徒の可能性を最大化するStudyコーデにインタビュー

オンライン塾が増える中、本当に効果があるのか不安に感じる方も多いでしょう。今回は、全国対応のオンライン塾「Studyコーデ」代表の名川先生にインタビューしました。「放置しない」という独自コンセプトで、徹底した学習管理と個別サポートを実践する同塾の取り組みに迫ります。地方の教育格差解消への思いから生まれた、新しい学びの形をご紹介します。

- 名川 祐人(ながわ ゆうと)先生
- Studyコーデ代表。慶應義塾大学経済学部卒 キーエンスで営業マンを6年務めたのち大学受験業界へ。 2020年にStudyコーデを設立し、現在に至る。勉強から進路相談まで、大学受験の全過程に寄り添った指導をモットーに、中3生から浪人生まで年間の生徒との面談回数は2000回を越える。 Studyコーデでも多くの生徒は受け入れず、少数の生徒を丁寧に指導して合格に導いている。
全国対応のオンライン塾!地方の教育格差をなくす挑戦
——本日はよろしくお願いします。名川先生のお役職とお仕事について教えてください。
Studyコーデの代表兼講師をしております。他にも、英語専門の進学塾、総合型選抜の塾比較メディアなど、大学入試の対策を専門にした仕事をしています。
——塾を開いた経緯についてもお話うかがえますか?
子どもが生まれて、ライフスタイルの変化を考えていた時にコロナ禍が重なりました。もともと対面授業の塾で講師をしていて、コロナ禍でオンライン指導を試行錯誤する中で、オンラインでも適切な仕組みを作ればオフラインと同様に成績を上げられると感じました。
当時、地方から出てきた浪人生が一人暮らしをしながら東京で勉強する姿を見て、地方の生徒が不利な状況にあると感じていました。オンラインであれば授業料も抑えられるため、良い塾が近くにない生徒や、高額な授業料を払えない生徒にも指導できます。かつコロナのような外部環境に影響されない安心できる勉強環境を提供したい。そこで自分でオンライン塾を立ち上げることにしました。
放置しない学習管理~トータルコーディネートとは?
——平等な機会を提供したいという思いからオンラインで塾を始められたんですね。「放置しない」という特徴的なコンセプトについて教えてください。
生徒の成績を上げて第1志望校に合格させるには、1から10まですべてをケアする必要があります。塾のスタンスとして、可能な限り全てのサポートを提供したいと考えています。
最近では授業ではなく学習管理をメインにする塾も増えてきました。週間スケジュールを立てて週1回の進捗確認だけをする形式です。この場合、6日間は生徒が一人で勉強を進めるわけですが、計画通りに進められたかのチェックや、学習内容の復習のタイミングを誰が指導するのかという課題があります。
——授業も学習管理も行っているのですね。オンライン指導と「放置しない」という手厚いサポートの両立はどのように実現されていますか?
オンラインの最大の課題は「手軽さ」と「効果」のバランスです。手軽に受講できることがオンラインの利点ですが、手軽すぎると効果が薄れてしまう危険性があります。
成績を上げるには、細部までのアドバイスと一定の強制力が必要です。そこで私たちは「トータルコーディネート」という名称で、勉強計画の立案、授業、授業後の振り返り面談、確認テスト、自習内容の組み立て、そして進路指導や出願戦略まで、全てを手厚く提供しています。

——学習の継続性を保つために、どのような工夫をされていますか?
当塾ではZoomでの面談を頻繁に実施して、学習の継続性を確保しています。この面談は単なる質問応答ではなく、その日の学習内容について「今日の動画で重要な点は何だった?」「この概念はなぜ大事なのか説明してみて」といった形で口頭テストを行います。これにより生徒はわかった「つもり」から脱却し、本当の理解に到達できます。

オフラインの塾では教室に行くこと自体が強制力になりますが、オンラインではそれがありません。そこで小テストを多用し、結果で学習状況を可視化することで学習の質を高めています。テスト結果が悪ければ、学習方法や量を見直す機会にもなります。
こうした学習管理は年齢に関わらず効果的です。現役生だけではなく、浪人生の生活リズム作りにも注力していて、朝9時からの授業開始、開始連絡の義務付けなど、規則正しい生活を送れるよう工夫しています。これは特に地方の浪人生にとって、勉強環境を整える上で重要なポイントです。
——どのような生徒さんがStudyコーデを選ばれているのですか?
地域的には非常にバラバラで、北から南まで全国各地から受講いただいています。関東の生徒も多いですね。また、通信制高校の生徒や対面のコミュニケーションが苦手な生徒も多く在籍しています。
——オンラインであれば全国で受けられるので安心ですね。入塾から実際の指導の流れを簡単に教えていただけますか?
必ず面談を行い、塾のコンセプトを説明しながら生徒の状況をヒアリングします。塾選びはマッチングが重要なので、相性を確認し、場合によっては他の塾を勧めることもあります。面談後に無料の体験授業を3回受けていただき、オンライン学習の雰囲気や方法を体験してもらってから入会という流れです。
週3回の徹底指導~オンラインでも続く学習習慣の作り方
——カリキュラムや学習計画はどのように立てていますか?
高3の4月または浪人の4月に入塾した方が、必ず次に合格できるカリキュラムをベースにしています。それを生徒ごとの入塾時期や学力に合わせて調整していきます。
難関大学を志望する高1、高2が入会した場合、高3の内容よりも簡単なところから始めて、しっかりと基礎を積み上げながら長期スパンの戦略を立てていきます。

——高1段階で進路が決まっていない生徒に対してはどのような指導をされていますか?
まずは英語です。理系・文系、国立・私立どの進路を選んでも必ず必要になり、最も大事になってくるのが英語だからです。早期に英語を得意科目にする方針で指導しています。

——指導の頻度はどれくらいですか?
高3、浪人生は週3回の指導をしていきます。1日おきに続くのでタフですが、そのぶん鍛えられます。高1、高2は週2回の生徒が多いですね。毎回面談もしているので、手厚いサポートを提供しています。
——オンライン指導の場合、保護者は子どもが家でちゃんと勉強しているかがわかりにくいと思います。学習の継続を促すためにどのような工夫をしていますか?
当塾ではオンライン家庭教師のようにずっとZoomを繋いで1対1で教えるわけではありません。当塾が作成した動画や、場合によっては参考書やプリント教材を生徒が2〜3時間かけて学習します。
学習が終わったタイミングで連絡をもらい、その後Zoomで講師と面談します。このとき、ありがちな「わからないことがあった」という受け身の姿勢を待つのではなく、講師から積極的に「今日の動画で何が大事と言っていたか説明してみて」「覚えるべき3つのポイントを言ってみて」といった口頭で確認の質問をします。
この授業内容を受けた後の振り返りと理解の定着が、成績向上に役立ちます。実は生徒自身が「わかっていないこと」に気づいていないケースも多いので、多角的な質問で理解度を確認し、不十分な点はその場で解説します。毎日の学習内容を確実に消化してから次に進むというやり方です。
毎年卒業生から「全くさぼれない」と言われます(笑)。受講後のZoom面談で講師から質問されることがわかっているため、動画授業であっても集中して内容を理解し、暗記せざるを得ないからです。こうして強制力を生み出しながら、日々の学習の質を高めています。
——毎回チェックが入るならば生徒は気を抜いて勉強できませんね。
基本的にテスト結果で評価しています。毎回の授業では必ず小テストを実施し、前回の授業の内容の確認テストや英単語テストなど、1日に4〜5種類ものテストがあります。授業のない日も翌日のテスト勉強に充てる形になり、自然と学習サイクルが確立されます。
テスト結果が不十分な場合は、前日の学習量や方法を確認し、必要に応じて修正していきます。結果を見て個別指導するアプローチです。暗記でテストだけ上手くすり抜けることがないように、面談で深く理解度を確認するようにしています。

——入念に仕組み化されているのですね。
Dropboxを活用して生徒ごとの個人フォルダーを作成しています。そこにカリキュラム資料を常時置いておき、また日々の授業コンテンツも随時更新していくスタイルです。生徒はいつでも自分の学習計画や成績を確認できる仕組みになっています。
また、動画教材も生徒はいつでもアクセスできます。この教材は私が作成しています。市販の教材も使用しますが、勉強が苦手な生徒は本を読んだだけでは理解できないことが多いので、しっかりと解説した動画を作成し、プリントや参考書と併用しながら視聴してもらいます。
——添削指導など、双方向のやりとりも対応していますか?
はい、総合型選抜の対策として、小論文・エッセイ・志望理由書の指導を行っています。活動実績作りという表面的なアプローチではなく、一般選抜入試とのバランスを重視しています。高校生自身ではこのバランス管理が難しく、どちらかに偏りがちなので、プロの講師がスケジュールを立て、適切な配分で両方で合格できるチャンスを残すサポートを行っています。
さらに、総合型選抜対策と一般入試対策のバランスを考えた指導方法のブラッシュアップも進めていきます。ただ活動実績を作るだけでなく、生徒自身が将来について考える機会を提供し、より意味のある受験準備になるよう導いていきたいと思います。
——保護者とのやりとりはよくありますか?
はい、保護者とのコミュニケーションも大切にしていて、生徒が学習につまずいた際には、家庭での援護射撃をお願いすることもあります。定期的なレポート送付で済ませるのではなく、必要に応じて連絡を取り合う関係性を構築しています。
先ほどご質問いただいたように、自宅にいてもオンラインで自室で学習している子どもの様子は把握しづらいため、不安なことがあれば連絡を取り合って確認するようにしています。
講師に求めるのは話す力より聞く力~ビジネス経験を活かした責任ある指導
——生徒数と指導体制について教えてください。
当塾は社会人プロ講師3名の体制で、生徒数は毎年40〜50名ほどしか受け入れられません。その代わり、一人ひとりにとても丁寧に指導するという方針です。講師1人あたりの担当生徒数を抑えることで、きめ細かい指導を可能にしています。
——講師陣はどのような方々ですか?
講師は3名とも、最初から塾講師や教師だったわけではなく、東証一部上場の企業で働いていた経験を持っています。Zoomでの1対1面談は、教室での対面授業よりもコミュニケーション能力が重要だと考えています。逃れられない1対1の状況で、生徒との信頼関係を築く人間性と責任感が不可欠です。
現在の講師は2人とも私が学生時代からよく知っており、ビジネスパーソンとしても信頼できる人間にしか声をかけておらず、むやみに講師陣を拡大する予定もありません。
——講師に求める資質や能力で特に重視しているものは何ですか?
一番は責任感です。「放置しない」というコンセプトをもとに1から10まで面倒を見るというスタンスなので、生徒の人生に真剣にコミットし、そのために自分の仕事をしっかりとやり遂げる責任感の強さを重視しています。
また、講師として話す力よりも聞く力を大切にしています。一見順調に見える生徒も、不調な生徒も、表情やテスト結果、言葉などからさまざまなメッセージを発しています。その背景にある本質的な課題をしっかり汲み取れないと適切なアドバイスができません。
私はかつてキーエンスで営業をしていました。優秀な営業マンは話す力よりも傾聴力が高いものです。相手の課題をしっかり把握した上でサポートする姿勢は、受験指導にも通じるものがあります。
受験を人生の成功体験にできる場所を目指して
——生徒にとってどんな存在でありたいですか?
大学受験は諸刃の剣だと思っています。この通過儀礼がメンタルを病ませたり、自己肯定感を下げたりするケースもある一方で、自分なりに努力してがんばり抜き、納得のいく結果を掴めれば、人生における大きな自信となります。
私たちはマイナスの事例も多く見てきたからこそ、「トータルコーディネート」という手厚いサポートのコンセプトが生まれました。生徒にとって「何でもプロに相談でき、安心しながら受験を人生の成功体験にできる場所」でありたいと考えています。
——いま塾を探している保護者へのメッセージをお願いします。
特に初めての受験生を持つ保護者の方は、受験制度の複雑さや塾の選択肢の多さに不安を感じることが多いと思います。お子さまにとって一生に一度の大きな挑戦だからこそ、どんなガイドをつけるかが重要です。
受験を成功させるためには当たり前のことを丁寧に積み重ねることが大切です。授業を受けたら振り返りをし、小テストで理解度を確認するという基本的なサイクルを確実に回していく先にしか成功はありません。
私たちプロの講師は少し口うるさいかもしれませんが、お子さまの状況を細かく見守り、適切な指導を提供します。保護者の方にとっても安心できるパートナーでありたいと考えています。
近くに大学受験に対応した塾がない方、通信制高校の生徒さん、そして浪人生のみなさんに、ぜひ当塾のサポートを活用していただければと思います。面談・体験授業を通じて、ご自身に合った学習環境かどうかをぜひ体感してください。
——今後のStudyコーデの展望を教えてください。
現在は社員3名で年間40〜50名の生徒を指導しています。この少人数制と手厚い指導は今後も維持していきたいと考えています。拡大よりも質の向上を追求する方針です。
また先ほどお話しした浪人生へのサポートもさらに充実させていきます。現在の予備校は現役生重視の傾向が強まり、浪人生の環境が限られているので、当塾が浪人生にとっての学びの場、心の支えになれるよう努めていきます。
最終的には、大学受験を通じて生徒が自信を持ち、その先の人生に活きる経験にできるよう、サポートの質を高めていくことが目標です。受験はゴールではなく、その先の人生のためのプロセスとして有意義なものにしていきたいと考えています。
受験は人生における大きなハードルですが、それを乗り越えた先にある達成感と自信は、その後の人生の糧となります。一緒にがんばりましょう。
——本日はありがとうございました。
取材協力:Studyコーデ