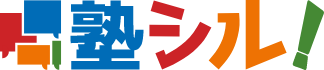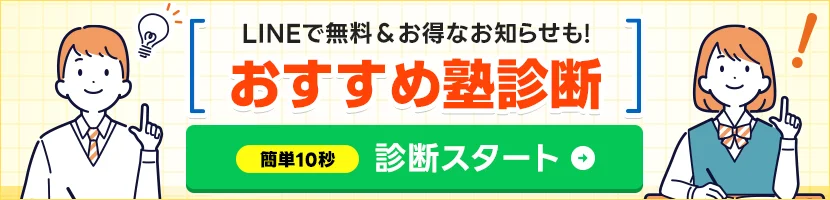【自信を失った生徒に寄り添う塾へ】個別指導塾TESTEAが貫く完全1対1の個別指導

2006年の創業以来、完全1対1の個別指導に定評のある個別指導塾テスティー。現在、首都圏に8教室を展開し、中学受験から大学受験まで一貫した指導体制を整え、成績が伸び悩み自信を失った生徒に寄り添うことを大切にしています。大学生講師の育成にも力を入れる同塾の創業者であり塾長の繁田和貴先生に、塾の理念や特徴についてお話をうかがいました。

- 繁田 和貴(はんだ かずたか)
- 個別指導塾TESTEA代表取締役社長。小学生時代にSAPIXで3年連続1位の成績を収め、開成中・高を経て東京大学経済学部を卒業。東大在学中に目標を見失って3回留年し、卒業後は自身の反省から「受験で終わらない、一生モノの人間力を」という理念のもと2006年にTESTEAを開校。生徒一人ひとりに寄り添って勉強法とモチベーションを改善し、男女御三家をはじめとする難関校に多数の逆転合格を出している。著書・メディア出演多数、中学受験生のお母さん向けメールマガジンやYouTube、Instagramでも情報発信を続けている。
8教室体制へと成長、オンライン指導も展開
ーー塾を創業してから現在までの流れについて教えていただけますか?
2006年にテスティーを立ち上げました。当初は共同創業者がいて副社長という立場でしたが、塾長としての役割は立ち上げ時から担っていました。2011年に私自身の会社として運営することになりました。

当時はまだ西永福校と久我山校の2教室のみでしたが、そこから少しずつ私自身が塾長として複数校舎を見る形に移行し、各校舎に教室長を置く形で展開しています。2年に1教室ぐらいのペースで拡大し、2018年に校舎を出したのを最後に、コロナ禍で5年間は新規展開を止めていました。
2023年から再び展開を開始し、2023年10月に田町校、2024年2月に初台校、11月に市ヶ谷校を開校。現在は8教室体制となり、リアルでの教室展開のスピードを徐々に加速させています。

ーー今後リアルの教室を増やしていくとのことですが、オンライン対応はありますか?
はい、遠方にお住まいでオンラインで受講したいというお声は以前からあるので、オンライン指導も対応しています。オンライン指導は実は10年以上前からやっていました。大々的には宣伝してなかったのですが、コロナ禍になって状況は大きく変わり、オンライン指導にしかない良さにも気づきました。
ーーどのような点でしょうか?
英語の長文や国語の読解問題で、文章をそのままホワイトボードに全部書いて生徒に写してもらうのは指導の時間の使い方としては正しくないと思っています。
オンラインなら画面共有をすればPDFファイルを取り込むことができますし、データとしてアーカイブしておくことができるので、これはオンライン指導の大きなメリットです。今後もリアルの教室を展開しつつ、オンライン指導も継続していきます。

開成「番長」は弱き者の味方を目指す
ーーつづいてテスティーの指導方針について教えてください。
テスティーは開校当初から完全1対1の個別指導でやっていて、「受験対策や定期試験対策に強い」ことを売りにしています。多くの個別指導塾は高校受験の対策がメインですが、当塾はまず中学受験に強みがあり、そして進学してからの中高一貫校の進度の早いカリキュラムのサポート、その上での大学受験対策をします。中学受験をする生徒が進学後もずっと同じ塾に通える形になっているのは大きな特徴です。
ーーその設計は繁田先生のご経験に由来するのでしょうか?
まさしく自分の経験に由来します。私は中高一貫校を経て大学受験を経験しました。自分のようなパターンで中学受験をして一貫校に入ったものの、ちょっと落ちこぼれたり、途中でさぼったりする時期が来る生徒は多いのです。その時期をサポートしながら、大学受験まで導いて、もし叶うならそのまま講師としてまたテスティーに戻ってきて、自分が指導してもらった経験を活かして後輩たちを温かく導いてほしい。そんな循環を持った学びの場を目指しています。
ーー教室展開が増えていっても上位層の対策という方針は同じですか?
これは完全に誤解されているんですけど、そうじゃないんです!と言わせてください(笑)。私が「開成、東大卒」であったり「開成番長」と名乗っているせいで「テスティー=上位層向けの塾」と思われがちなんですけど、開成番長の中で強調したいのは「開成」じゃなくて、「番長」の方なんです。弱き者の熱き味方でありたい。
ーーずっと上位層向けの塾だと思っていました!
多くの方がそう思っています(笑)。でも実際には、成績が上がらなくて自信をなくしている子供に「大丈夫だよ!」と温かく寄り添ってサポートする塾なのです。ですので上位校狙いの生徒しか通わないということはありません。もちろん上位校を狙う子もいるのですが、1番多いのはやっぱり中堅校を狙っている子です。偏差値でいうと40台の生徒が、うちがもっとも価値を発揮できる子たちです。
開校してから5〜6年前までは、高校生が一番多く在籍していました。あるとき中学受験の指導をしっかりとやれる塾があまりなかったことに気づき、「当塾は中学受験か大学受験まで一つの塾で対応できます」とお伝えしたところ、自然と小学生の保護者からのお問い合わせが増えました。
ーーいま深刻な少子化ですが、中学受験への影響を感じることはありますか?
中学受験は少子化になってもニーズが落ちていないんです。子供は確かに減っていますし、ひとりっ子も増えていますが、そういう状況だからこそ「たった1人の我が子にいい教育を」という保護者の方は多いです。
一方で中学受験をしっかり指導できる講師を集めるのは簡単ではありません。これまで中学受験では年齢でいうと30~50代の経験値の高い講師が指導の中心となってきました。しかしこれから個別指導のニーズがどんどん高まっていくならば先生の数が必要になります。それでも「若手講師を育ててやっていこう」という塾は本当に少ないなと思っていました。「あ、君、早稲田なの、すごいね!じゃあ任せたよ!」みたいな感じで、ロクに研修もしない塾は本当に多いです(苦笑)。
でも中学受験をしっかりサポートしようと思うなら、講師をきちんと育てないとダメなんですよね。きちんとやる塾が少ないからこそ、我々は使命感を持って講師育成に取り組んでいます。
また、親子の関わり方を中心とした親の正しい知識も必要です。そういった情報を2019年からメールマガジンで発信し始め、その後SNSやYouTube、インスタグラムなども活用して発信し続けています。5~6年前までは高校生が多かったのですが、気づけば今は中学受験生が一番多くなっています。

1対1の指導でしか伝えられないこと
ーー1対1の授業スタイルについてお聞きします。多くの個別指導では「1人を教えている間に別の生徒に演習をしてもらう方が効率的だ」という指針のもと、講師1名に対して複数の生徒を教えるスタイルを取っています。1対1を貫く理由を教えていただけますか?
そのスタイルは「別の子を教えている間は自分で解いてください」ということですよね。たしかに業務効率を上げることはお客さんのためでもあると言えますし、1対2にすることによって価格を下げるのであれば保護者にもメリットはあるでしょう。
しかし経験上、勉強で成績が伸び悩んでいる子というのは、その解いているプロセスとか、ノートの使い方とか根本の学習のやり方に問題がある場合が多いのです。そういった細部をしっかりと見た上で、一つずつ解消していくには、やっぱり1対1じゃないと難しいです。
もっと言ってしまえば「1人が解いている間に、もう1人に解説して」って、「そんなに素早く反応できるほど、先生たちは頭いいですか?」というのが本音です。
ーー複数名を同時に指導するには高度なスキルが必要ということでしょうか?
別の生徒を教えながら、見た瞬間に即答、即解説ができる問題ばかりですか? と疑問に思います。先生がその範囲だけしか教えないということであればできるかもしれませんが、現実的にその場で対応しなきゃいけないものも多いのです。
正解を教えるだけなら簡単です。しかし正解は一つであっても、理解してもらうために複数の過程を用意しなければなりませんし、それは生徒ごとに変わります。1対2名以上で指導していると、結局「1人の解説に先生が考え込んじゃって、もう1人の方も問題解き終わって待たせてしまう」みたいなことが起こります。

ーー問題や教え方、さらに生徒の理解によっては難しいと思います。
一般的な公立中学の内容なら対応できる講師は多いでしょう。成績3ぐらいの子の数学は難しくありません。でも、中学受験生に対して1対2で手厚く指導するなんて無理ですよ。中学受験の問題は、大学受験よりも難しいものもあります。中学受験に実際に素早く対応できる先生なんて、ほとんどいないはずです。
プロの講師が1対1でやっているものを、学生講師が1対2でできるわけがないと思っています。レベルによっては1対2でいけるケースもあることは理解していますが、当塾としては「1対2で受けたい人は、他の塾をおすすめします」と伝えています。あと、実は1対1で指導することの本質的な意義かつ最大のメリットは、まだ他にあるんです。
ーーそこはぜひ詳しくお聞きしたいです。
成績が伸び悩んでいる子が知らず知らずのうちに陥っているのが、「わかったつもり」の状態で放置してしまうという罠です。これは大手塾や学校など集団授業の構造的な欠陥だと思っているのですが、授業中に説明を聞いて「あれ、よくわからないぞ」と思っても授業中にその場で質問することは難しく、また授業後に質問に行くこともなかなかできないものです。
そうすると中途半端な理解で放置することが増え、やがてそれが当たり前になり、「わかったつもり」で終わらせる悪い癖がついてしまいます。これって本人は悪気なく、ちゃんと「わかった」と思っているから厄介なんですよね。本人の中の感覚・理解度の話なので、宿題をやった/やらなかったなどとは違って外から見えづらく、致命的なエラーであるにもかかわらず気づかれにくいのです。その結果、「わかったはずなのになぜかテストになるとできない」ということが頻発します。これまでの指導経験上、大なり小なりこのトラブルを抱えている生徒は8割以上います。
ーーなるほど。本番で力を発揮できないの普段の勉強や授業の受け方に原因があると言えますね。テスティーではそういった問題が起きないようにどのような工夫をしているのでしょうか?
この「わかったつもり」を正しい「わかった」に矯正するためのもっとも有効な方法が、「問いかけ」をすることなのです。「なぜこういう式になるのか先生に説明してみて」というような問いかけです。
たとえ流暢な説明ではなくとも、きちんと手順を追って説明できていれば正しくわかっているといえますし、うまく説明できなければ正しい「わかった」ではなく実は「わかったつもり」だったということになります。定着のためには正しい「わかった」のラインにまで理解度レベルを持っていくことが必要で、このラインを我々は「ステイライン」と呼び、授業の際に非常に重要視しています。
知らず知らずのうちに陥っていた「わかったつもり」の罠から抜け出し、自らのステイラインをきちんと把握できるようになることは、成績アップの肝であり、一生役立つ己の感覚となります。これに気づかせるのは問いかけです。そしてこうした問いかけ重視の双方向型授業は、1対1の講義形式でやらなければ難しいのです。
あと、教科内容の指導とは別の観点で、1対1ならじっくり90分間、ひとりの先生を独占できるので、特に高校生とか中学生だと勉強以外の話から受ける影響も大きいです。雑談とか教養的な雑学といった類の話から、その先輩の生き方や考え方をトレースするみたいな、そういった時間を作れるのです。
その中で自分の目標が明確になり、学習のやる気が上がります。そういうのも1対1の方が良いと思っています。1対2形式で科目内容の解説だけをやっていたら、なかなかそういう時間を取れないと思います。

中高一貫校の「中だるみ」を支える大学生講師
ーーなるほど。そういったメリットもあるわけですね。講師はどんな方が多いのでしょうか?
大学生講師が9割以上です。以前は東大生メインで採用をしていましたが、今は結構大学の範囲を広げています。東大早慶の学生中心なのは間違いないんですけど、それ以外にも、医学部の学生とか、東工大一橋、もちろんマーチ(MARCH)の学生も活躍しています。
ーー大学生講師が指導で価値を出せるのはどういった点ですか?
中高一貫校に通う多くの生徒には「中だるみ」が起こります。授業の内容を理解できないまま進んでしまうことが原因なのですが、早期に適切な指導をしなければわからない点が積み重なってどんどん遅れていきます。
「ちゃんとわかる」という状態を積み重ねるために、当塾の授業では改めてインプットし直す。場合によっては1年以上も前の内容に戻ってインプットし直すこともあります。
思春期や反抗期でやる気がなくなることはよくあって、そういう時期に親の言うことは聞いてくれません。しかし、大学生の先生の話はしっかり聞いてくれます。「大人の話は聞きたくないけど、兄貴分の話は聞く」という心理状態になりやすいのです。
ーー中だるみのポイントをうまく乗り越えるには大学生講師の方がいいということですね。
はい、ここは大学生がベストだと確信しています。優秀な大学生をしっかり育成していくことも当塾の強みの一つです。

テスティーが理想とする講師とは?
ーー講師の採用で重視されている点を教えていただけますか? マッチングはどのように決めていますか?
人柄がめちゃくちゃ大事です。そこに加えて学力・学歴があったらベターという感じですね。つまり学歴があったとしても人柄がダメだったら採用しません。
素直で明るい講師が理想です。素直だったらこちらのフィードバックをうまく受け止めて成長しますし、塾の雰囲気もよくなります。生徒に対してプラスのオーラを与える人を求めています。
マッチングに関しては、生徒の学力や性格も判断材料にしますが、生徒の志望校に対して合格に導けるかを重視しています。
ーー研修体制についてはいかがでしょうか?
中学受験の指導について、保護者がもっとも不安に思うことは講師のレベルが安定しないことなのです。そこでテスティーでは採用研修の専門チームを用意しています。採用から研修まで管理しているので、塾業界によくある「いきなり教室に送り込まれて授業を丸投げされる」みたいなことはありません。講師の指導レベルを高く保つために採用研修専門の部署があることも当塾の一つの強みです。
生徒たちが自信を取り戻せる場所でありたい
ーー最後に、塾として大切にされていることや、保護者の方へのメッセージをお願いできますか?
風邪を引いたら病院に行くように、勉強でつまずいたときの相談場所でありたいと考えています。いま成績が伸び悩んでいる、自信をなくしている、勉強が苦手だと思っている生徒さんこそ、第一歩を踏み出してほしいと思います。
正しい勉強法は、知れば知るほど、早ければ早いほど、その効果は複利のように効いてきます。勉強のやり方を身につけ、「できた」という自信を得ることは一生の財産になります。ただ漠然と時間をかけるのではなく、効率的な勉強法を早めに身につけることで、学習の質が大きく変わってきます。
私たちは一人ひとりの話をしっかり聞いて、具体的な改善策を一緒に考え、丁寧に説明しながら寄り添っていきます。塾に来ることが負担ではなく、むしろ「気持ちが楽になる」「勉強が楽しくなる」と感じられる場所を目指しています。
成績アップはもちろんですが、それ以上に「自分でできる」という自信をつけ、「自己肯定感」を高めてもらうことを大切にしているので、ぜひ早い段階でその一歩を踏み出していただければと思います。
ーー本日はありがとうございました。
取材協力:個別指導塾TESTEA